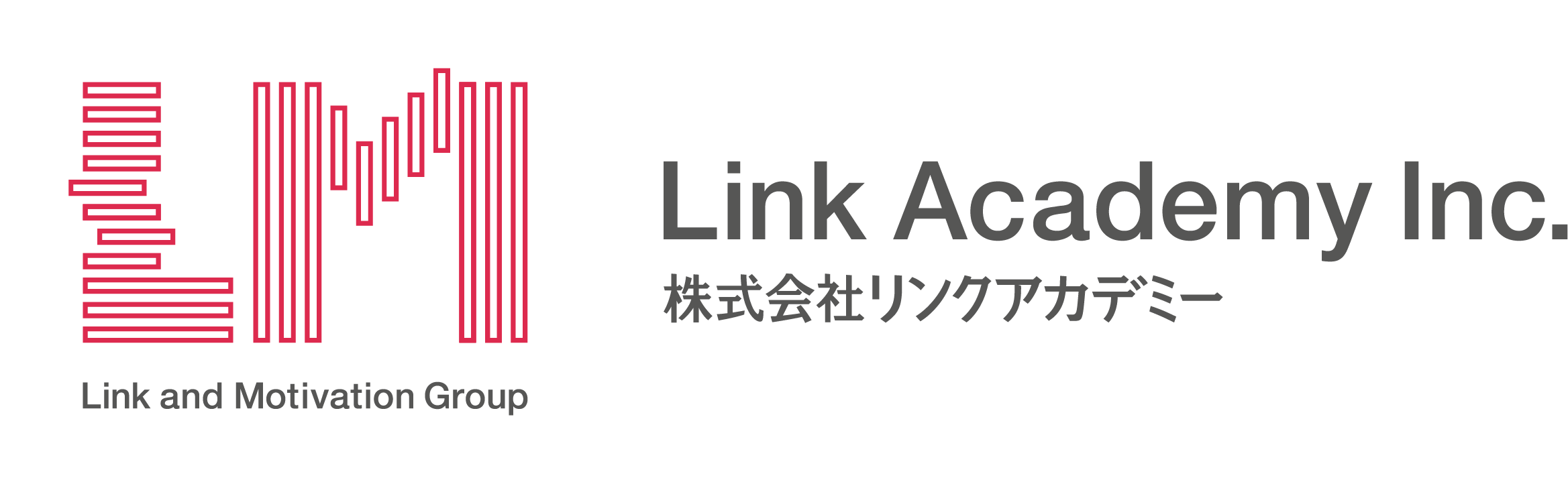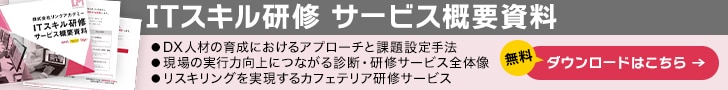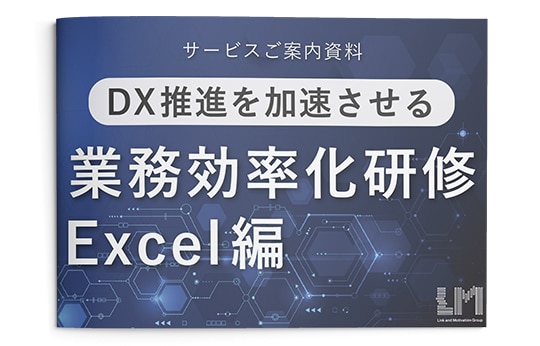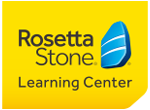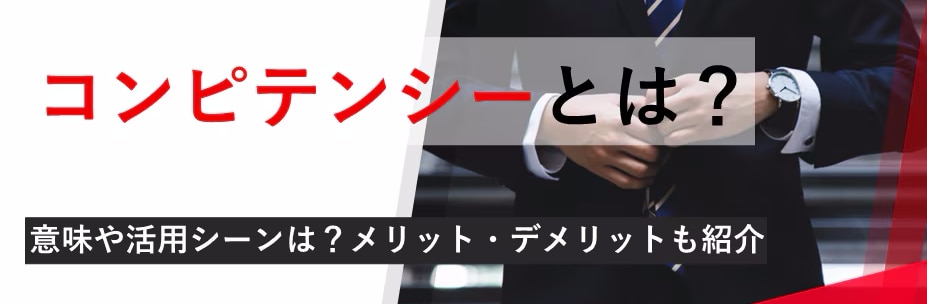
コンピテンシーとは?意味や活用シーンは?メリット・デメリットも紹介
目次[非表示]
- 1.コンピテンシーとは何か
- 2.コンピテンシーが生まれた背景とは?
- 3.コンピテンシーモデルとは
- 4. コンピテンシーモデルの種類は
- 4.1.実在型モデル
- 4.2.理想型モデル
- 4.3.ハイブリッド型モデル
- 5.コンピテンシーの活用シーン
- 6.コンピテンシーのメリット・デメリット
- 6.1.コンピテンシーのメリット
- 6.2.コンピテンシーのデメリット
- 7.コンピテンシー評価について
- 8.コンピテンシー面接について
- 9.コンピテンシーの導入方法・手順
- 9.1.コンピテンシーの目的を明確にする
- 9.2.ハイパフォーマーへのヒアリングを実施する
- 9.3.コンピテンシーモデルとして整理する
- 9.4.振り返りの機会を設ける
- 10.コンピテンシーに基づく従業員スキルの強化研修ならリンクアカデミー
- 11.記事まとめ
- 12.コンピテンシーに関するよくある質問
人事評価や面接などのタイミングで、「コンピテンシー」という言葉を目にすることがあるのではないでしょうか。コンピテンシーは、多くの企業で導入、または注目されているものであり、コンピテンシーを活用することで人事評価や人材育成をより効果的なものにすることができます。本記事では、人事領域で注目されているコンピテンシーについて、その意味や活用シーン、メリット・デメリットなどをご紹介します。
コンピテンシーとは何か
コンピテンシーとは、「技能」や「能力」、「適性」といった意味を持つ英語である「competency」から来ている言葉です。コンピテンシーはビジネスシーンでは「優秀な従業員に共通している行動や思考の特性」といった意味として用いられており、採用や人事評価で主に活用されています。
コンピテンシーは、「ハイパフォーマーは普段どのようなことを考えているのか」や「起こったことに対してどのような行動をしているのか」といったことの、分析・整理をすることで決めることができます。行動や考え方だけではなく、行動や思考に繋がっている価値観や経験、性格などもコンピテンシーに含まれています。
コンピテンシーとコア・コンピタンスの違い
コンピテンシーと似ている言葉として、「コア・コンピタンス」があります。コア・コンピタンスとは、企業が価値発揮を行うために持っている特性や技術のことを指します。「他社には真似ができない高い技術力」や「1つの事業で活用している資源を、他の事業に応用して多角化する力」、「優秀な人材を確保できる採用力」など、その内容は様々です。
「成果を出すための源泉になるもの」といった点では、コンピテンシーとコア・コンピタンスは同様の意味を持っています。しかし、コンピテンシーが個人を対象にしているのに対して、コア・コンピタンスは企業や組織を対象にしている点で異なります。
コンピテンシーとスキルの違い
「スキル」は、しばしばコンピテンシーと混同して用いられる言葉の1つです。スキルとは、英語で「技能」や「技術」を意味しており、ビジネスシーンでは営業スキルやITスキルといった使われ方をしています。スキルが高まることで、従業員はパフォーマンスを向上してより良い成果を創出することができるため、コンピテンシーと同じように感じるかもしれません。
スキルは技術や技能そのものを指しており、それを発揮するためのアクションができなければ、結果には結びつきません。この「スキルを発揮するためのアクション」を起こすことができる要因となるのが、コンピテンシーです。コンピテンシーがある、コンピテンシーを高めることができれば、従業員は持っているスキルを発揮することができるようになり、全体の成果も向上することが期待できます。
▼スキルを向上するスキルマップについて詳しい解説はこちら
コンピテンシーとアビリティの違い
スキルと同様に、「アビリティ」もコンピテンシーと近い言葉として認識されています。アビリティとは、英語の「ability」から来ており、「能力」や「才能」といった意味を持っています。スキルと似ている言葉ですが、スキルが「特定の業務の遂行に必要な専門知識・技術」という意味であるのに対して、アビリティはより広く「職務全体を担うために必要な能力」といった意味を持っています。
また、「才能」という意味を持っているため、後天的なものよりも先天的なものを指すように感じますが、実際には後天的に獲得したものもアビリティとして考えます。コンピテンシーとの違いとしては、スキルと同様に、アビリティが技術や技能そのものを指すのに対して、コンピテンシーはアビリティを発揮するための要因を指しているといった点で異なります。
コンピテンシーとリテラシーの違い
コンピテンシーとリテラシーは、両方とも能力やスキルを示す言葉ですが、それぞれに異なる意味があります。
コンピテンシーは、特定のタスクや職務を遂行するために必要なスキルや知識を指します。例えば、プログラミングのコンピテンシー、経理のコンピテンシーなどがあります。
一方、リテラシーは、ある特定の分野に関する知識やスキルだけでなく、さまざまな分野で必要とされる基礎的なスキルや知識を指します。例えば、読み書きのリテラシー、デジタルリテラシーなどがあります。
つまり、コンピテンシーは狭義で深い知識やスキルを示し、リテラシーは広義で基礎的な知識やスキルを示します。
コンピテンシーが生まれた背景とは?
コンピテンシーは、1950年代に心理学の用語として生まれたと言われています。その後、ハーバード大学の心理学教授であるマクレランドが、学歴や知能レベルが同程度の職員で業績の差が出る原因を調べた結果、コンピテンシーの違いに原因があることを発表したことで注目を集めるようになりました。マクレランド教授が行った調査の結果、下記のようなことが判明しました。
■職員の学歴や知能レベルは、発揮するパフォーマンスとそれほど相関がない
■高いパフォーマンスを発揮している職員は、それぞれ特有の行動特性を持っており、思考の特性にも特徴や共通点がある
この調査以降、1990年代にはアメリカで人材育成や人材採用のシーンでコンピテンシーが活用されるようになりました。また、日本でも高度経済成長期以降に従来の年功序列の制度が機能しなくなってきたタイミングで、成果を向上させるための仕組みとしてコンピテンシーが注目されるようになりました。
加えて、現在の日本は少子高齢化の影響により、労働人口が減少傾向にあることが大きな問題として提唱されています。そのため、効果的な人材育成のためには「能力」といったものからより、成果創出のために根源的な要因であるコンピテンシーに焦点を当てた育成・評価手法が重要になっています。
コンピテンシーモデルとは
コンピテンシーを分類して整理したものを、コンピテンシーモデルと言います。
コンピテンシーのモデル化については、コンピテンシーマップの作成につながる重要なプロセスとなっています。コンピテンシーマップは、組織が必要とするすべてのコンピテンシーを一覧にすることで、従業員が必要なスキルを習得するための教育プログラムを作成するための基礎となります。
コンピテンシーマップの作成には、いくつかのステップが必要です。まず、組織が必要とするコンピテンシーを明確に定義することが重要です。これには、職務分析や業務プロセスの分析を行い、必要なスキルや知識を特定することが含まれます。次に、それらのコンピテンシーを詳細に描写し、それらがどのように実践されるかを説明することが必要です。このプロセスには、コンピテンシーの定義、習得するためのスキルや知識、教育プログラム、評価方法が含まれます。
コンピテンシーモデルを活用することで、網羅的にコンピテンシーの活用をすることができるでしょう。
コンピテンシーモデルの種類は
コンピテンシーを抽出、整理する際にはいくつかのパターンがあります。ここでは、主なコンピテンシーモデルの考え方についてご紹介します。
実在型モデル
実在型モデルとは、現在成果を創出している従業員の行動や考え方からコンピテンシーを抽出するモデルです。一般的に、成果を出すことができる従業員にはある程度共通した特徴があると言われています。実在型モデルでは、そのような従業員の行動や考え方を参考にして、成果を出すために必要なコンピテンシーを抽出します。
実際にいる従業員からコンピテンシーを抽出するため、具体的な目標設定が行いやすいというメリットがあります。
理想型モデル
理想型モデルとは、会社にとって望ましい人材が行うであろう行動や考え方からコンピテンシーを整理するモデルです。自社にとって理想的な人材を仮定して、その人材がどのような行動や考え方をするのかをイメージします。
理想型モデルでは、企業ごとの特色を反映した理想の人材像を設定することになるため、今後必要になるスキルや能力といったものも考えることができる部分がメリットになります。自社内にロールモデルとなる従業員がいない場合や、新しい事業を展開する場合などに向いています。
ハイブリッド型モデル
ハイブリッド型モデルとは、実在型モデルと理想型モデルを組み合わせたモデルです。自社内で成果を出すことができている従業員の行動や考え方を整理するとともに、理想の人材についても考えて、そのコンピテンシーを組み合わせる方法をとります。
ハイブリッド型モデルを活用することで、実際に成果を出している人のコンピテンシーを抽出するとともに、今後必要になるコンピテンシーについても盛り込むことができます。
コンピテンシーの活用シーン
人事評価
コンピテンシーの活用シーンとして、最も有名なものが「人事評価での活用」でしょう。高度経済成長期以降は、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。顧客のニーズの多様化や、情報化社会の発展などによって、一度売れた商品・サービスが売れ続けるということは少なくなってきました。また、働き手の意識の変化によって転職や副業が当たり前になってきています。
そのため、成果創出が直接的に人事評価に繋がる制度を導入する企業は増えてきており、その1つとしてコンピテンシーによる人事評価が注目されています。コンピテンシーを評価に活用することで、曖昧な評価基準ではなく、成果創出に必要な行動特性や思考特性について評価ができるようになります。
人材採用
人材採用のシーンにおいても、コンピテンシーが活用されることが多くなっています。採用のタイミングでミスマッチが起こってしまうと、企業側にとっても従業員側にとっても機会損失が大きくなってしまいます。そのため、これまでも効果的な面接の手法や選考基準などが多く検討されてきました。
コンピテンシーは、実際に企業の中で高い成果をあげているハイパフォーマーに共通する行動特性や思考特性から考えられているため、採用時点でコンピテンシーを基準にして選考を行うことで、自社で活躍できるかどうかを判断しやすくなります。経歴や職歴を確認する際には、その行動の裏にある理由や背景を自社のコンピテンシーと照らし合わせると良いでしょう。
人材配置
人材配置を検討・実施する際にも、コンピテンシーが活用されています。人材配置は企業の中でのフォーメーションを決定するものであるため、初期配置や配置転換の際には頭を悩ませることが多いでしょう。コンピテンシーを活用することで、より効果的な人材配置を行うことができるようになります。
例えば、なかなか成果を創出できていない従業員に対して、そのスキルが足りていないのか、所属している部署やチームと特性が合わないのかを、コンピテンシーを活用することで客観的に判断することができます。より本人の特性と合致する部署やチームがある場合には、そこに異動してもらうことで高い成果をあげるようになることが期待できるでしょう。
人材教育
最近、コンピテンシーを人材教育に活用する取り組みが増えています。コンピテンシーに基づく教育は、従来の学校教育や研修とは異なり、必要なスキルに集中して短期間で効果的に学ぶことができます。このようなアプローチは、現代のビジネス環境において、常に変化する市場や技術に対応するために必要な能力を習得するために役立ちます。
コンピテンシーを人材教育に活用することで、育成効率を高めるだけではなく、組織の生産性を高めることもできるでしょう。
例えば昨今のDXの流れに合わせて、コンピテンシーを抽出することで、データ利活用の出来る人材育成へのアプローチをかけることが可能になります。
コンピテンシーのメリット・デメリット
コンピテンシーのメリット
コンピテンシー設定のメリットとして、下記のようなものが挙げられます。
■生産性が向上する
コンピテンシーを人材育成に導入することで、生産性が向上することがメリットとして挙げられます。コンピテンシーは高い成果を創出するハイパフォーマーの行動特性や思考特性を分析して整理されるため、より育成に効果的な要素が分かりやすくなります。効果的な育成を行うことができると、業務のスピードやクオリティが向上するため、生産性向上にも繋がります。
■評価への納得感が高まる
従業員の行動特性や思考特性を育てるために、「やる気」や「根性」といった要素を評価で考慮する場合がありますが、従業員から「主観で決められている」といった受け止め方になる可能性があります。コンピテンシーとして明確な基準を設けることで、評価に対する納得感が高まるでしょう。
コンピテンシーのデメリット
コンピテンシーを導入する際に挙げられるデメリットとして、下記のようなものがあります。
■コンピテンシーを設定するのに時間がかかる
コンピテンシーを設定する際には、実際に成果をあげているハイパフォーマーにヒアリングを行う必要があります。部署や職種、役割ごとにコンピテンシーを設定する際には、多くの従業員にヒアリングを実施することになるでしょう。また、ヒアリングを行った後には収集した情報から自社のコンピテンシーとしてどのような分類や整理を行うのかを考えることになるため、設定にはある程度時間がかかります。
■定期的に更新する必要がある
一度コンピテンシーを設定したとしても、社会情勢や時代の変化によって企業に求められることも変化していきます。そのため、以前は成果をあげることに繋がっていたコンピテンシーも、時間が経てば陳腐化してしまう可能性があります。設定したコンピテンシーについて、定期的に見直す機会を設けることが大切です。
コンピテンシー評価について
コンピテンシー評価とは、コンピテンシーを評価項目に設定して評価を行うことを指します。コンピテンシー評価を導入する際には、自社内で高い成果をあげているハイパフォーマーの行動特性や思考特性を調査・分析する方法と共に、自社の求める人物像から設定する方法があります。また、設定するコンピテンシーとしては、全社として共通のものと、職種や役割に合わせた個別のものを決める場合が多いでしょう。
コンピテンシー評価のメリット・デメリット
コンピテンシー評価のメリット・デメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。
■コンピテンシー評価のメリット
・効率的な育成ができる
コンピテンシーを基にして評価やフィードバックを行うことで、より成果や成長に繋がる育成を標準化して行うことができます。
・評価の基準が明確になる
整理したコンピテンシーがあると、曖昧な評価ではなくなるため、評価者の評価のしやすさと被評価者の納得感を向上することができます。に繋がります。
■コンピテンシー評価のデメリット
・コンピテンシーの設定が難しい
コンピテンシーは行動特性や思考特性を調査・分析する必要があるため、基本的には難しい作業になります。更に評価に組み込む際には、他の評価項目との兼ね合いや評価基準の設定などを考える必要があります。
・コンピテンシーを定期的に見直す必要がある
設定したコンピテンシーは、市場の変化や社内の変化などに伴って機能しなくなる可能性があります。特に従業員数が増えた場合や事業形態、業務の特性が変化した場合などには、そのタイミングでコンピテンシーにも変化がないかを確認することが大切です。
コンピテンシー面接について
コンピテンシーを選考基準に取り入れる方法を、コンピテンシー面接と言います。応募者の持っている特性が、自社で活躍している従業員に共通している行動特性や思考特性とマッチしているかどうかを判断します。そのため、コンピテンシー面接では事実に基づいて応募者のコンピテンシーを評価するため、印象や感覚に基づいた評価の割合が減ることになります。
また、コンピテンシー面接は新卒採用だけではなく、中途採用や未経験者などの採用にも活用することができます。
コンピテンシー面接のメリット・デメリット
コンピテンシー面接のメリット・デメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。
■コンピテンシー面接のメリット
・ミスマッチを防ぐことができる
コンピテンシーは、自社で実際に活躍している従業員に対するヒアリングや分析から設定されるため、応募者が入社後に活躍できる人材かどうかを見極めやすくなります。そのため、「気持ちはあるけど、会社と合っていない」といった、採用後のミスマッチをコンピテンシー面接を活用することで防ぐことができます。
・選考基準を統一できる
従来の面接方法では、面接官になった従業員の主観や感覚に頼ってしまうことがありました。コンピテンシー面接では、聞いていく事実から自社のコンピテンシーと照らし合わせることになるため、面接ごとの選考基準のムラを少なくすることができます。
■コンピテンシー面接のデメリット
・コンピテンシー面接だけで採用の判断をすることは難しい
コンピテンシー面接は有用な手法ではありますが、コンピテンシー面接だけでは採用を決めることは難しいでしょう。コンピテンシー面接はあくまで1つの判断材料として、他の面接手法と組み合わせて総合的に判断する必要があります。
コンピテンシー面接の評価基準は?
コンピテンシー面接では、以下のような5つの段階で応募者を評価することができます。レベルが高くなるほど、能動的な行動を取ることができると判断されます。
■レベル1:受動的な行動
他の人に指示をされたまま動く特性を持っているレベルです。自身の意志が薄く、周囲に流されやすいといった評価をすることになります。
■レベル2:通常の行動
レベル1に比べて自立的な行動ができる一方で、あらかじめ決められていることをこなすことができる程度の特性を持っているレベルです。決められたことを遂行することはできますが、自主的に工夫をしたり提案をしたりといった行動は見込みにくいといった評価になります。
■レベル3:主体的な行動
自分で考えて行動する特性を持っているレベルです。決められた範囲の中でも、結果をより良くするための工夫や提案を行うことができるといった評価になります。
■レベル4:創造的な行動
現状の課題を解決するために、具体的な行動をする特性を持っているレベルです。自分から目標を設定して、適宜軌道修正を行いながら物事を推進できるといった評価になります。
■レベル5:パラダイムシフトを起こす行動
規定の枠組みにとらわれることなく、柔軟な発想や行動をする特性を持っているレベルです。現状を打破して、新しい価値を生み出すことができるといった評価になります。
コンピテンシーの導入方法・手順
コンピテンシーの目的を明確にする
コンピテンシーを導入する際には、「なぜコンピテンシーを導入するのか」といった目的を明確にしておくことが大切です。目的が明確でない場合には、「そもそもどういったコンピテンシーが望ましいのかがわからない」「従業員が重要性を理解してくれず、運用に乗らない」といったことが発生しやすくなります。
ハイパフォーマーへのヒアリングを実施する
目的が明確になった後には、ハイパフォーマーへのヒアリングを実施します。ハイパフォーマーの剪定方法としては、シンプルに業績を基準にするというものがありますが、「自社の理念を体現している」「目指す人物像にマッチしている」といった面でも選定基準を設けることで、より良いコンピテンシーの抽出を行うことができます。
コンピテンシーモデルとして整理する
ヒアリングによって収集した要素を分類して、コンピテンシーモデルとして整理します。コンピテンシーモデルを整理する際には、下記のようなことに注意しましょう。
■できるだけ具体的な要件を設定する
■運用を見越して、数が増えすぎないようにする
■適切な分類を行って、分かりやすいものにする
振り返りの機会を設ける
実際にコンピテンシーを人事評価や人材育成、採用シーンで運用する中で、生じてくる問題を解決するために振り返りの機会を設けることが重要です。また、短期間での見直しだけではなく、社会情勢や自社の方針などが変化したタイミングでは、必要なコンピテンシーも変化している可能性があるため確認ができる機会を設けましょう。
コンピテンシーに基づく従業員スキルの強化研修ならリンクアカデミー
先述したように、世の中の動きに伴う企業の状況によってコンピテンシーは変化するものです。
しかし、業種・業界問わず、昨今必要とされていて、今後も間違いなく必要となるものもあるのではないでしょうか。それが、「データの利活用」に関するコンピテンシーです。
急速にデジタル化が進み、様々なデータが飛び交う中で自分に必要な情報を都度適切に抽出し、活用できている人や、データをこまめに適切に蓄積し、企業が保有する膨大なデータを分析して、その結果をもとに適切な行動修正をするという基本的な思考がしっかりと根付いているでしょうか。
勘や経験ではなく、データに裏付けされた適切な思考・行動による業務効率化、その成果として生まれた時間を新たな価値創造に活かすことができる、これが現代においてどの業界でも必要とされているコンピテンシーであるものの、これはすぐに身に着けられるものではありません。
だからこそ、身近的に使用しておりイメージのしやすいものと組み合わせることで、少しずつデータ活用に向けた思考力を鍛えることを検討してみてはいかがでしょうか。弊社リンクアカデミーでは、日常的に私用するOfficeツールの活用力とデータ活用に向けた思考力を鍛えるプログラムをご用意しております。
昨今では多くの企業様に法人 研修の導入をいただいており、その中でもデータ分析に関する内容は非常に人気が高い研修となっております。社員のコンピテンシーを高めるための施策として、是非ご確認ください。
記事まとめ
コンピテンシーとは、高い成果をあげているハイパフォーマーに共通している行動特性や思考特性のことを指します。企業の中でコンピテンシーを抽出し、人事評価や人材育成などに活用することで、公平な評価やスピーディーな育成の実現に近づきます。コンピテンシーはハイパフォーマーへのヒアリングやコンピテンシーモデルの整理のために、ある程度工数はかかりますが自社に合ったコンピテンシーを運用することで得られるメリットは大きいでしょう。
コンピテンシーに関するよくある質問
Q1:コンピテンシーの重要性は?
A1: 日本でも高度経済成長期以降に従来の年功序列の制度が機能しなくなってきたタイミングで、成果を向上させるための仕組みとしてコンピテンシーが注目されるようになりました。
加えて、現在の日本は少子高齢化の影響により、労働人口が減少傾向にあることが大きな問題として提唱されています。そのため、効果的な人材育成のためには「能力」といったものからより、成果創出のために根源的な要因であるコンピテンシーに焦点を当てた育成・評価手法が重要になっています。
Q2:コンピテンシーの導入における注意点は?
A2: 下記のようなデメリットにも注意しておく必要があります。
■コンピテンシーを設定するのに時間がかかる
コンピテンシーを設定する際には、実際に成果をあげているハイパフォーマーにヒアリングを行う必要があります。部署や職種、役割ごとにコンピテンシーを設定する際には、多くの従業員にヒアリングを実施することになるでしょう。また、ヒアリングを行った後には収集した情報から自社のコンピテンシーとしてどのような分類や整理を行うのかを考えることになるため、設定にはある程度時間がかかります。
■定期的に更新する必要がある
一度コンピテンシーを設定したとしても、社会情勢や時代の変化によって企業に求められることも変化していきます。そのため、以前は成果をあげることに繋がっていたコンピテンシーも、時間が経てば陳腐化してしまう可能性があります。設定したコンピテンシーについて、定期的に見直す機会を設けることが大切です。