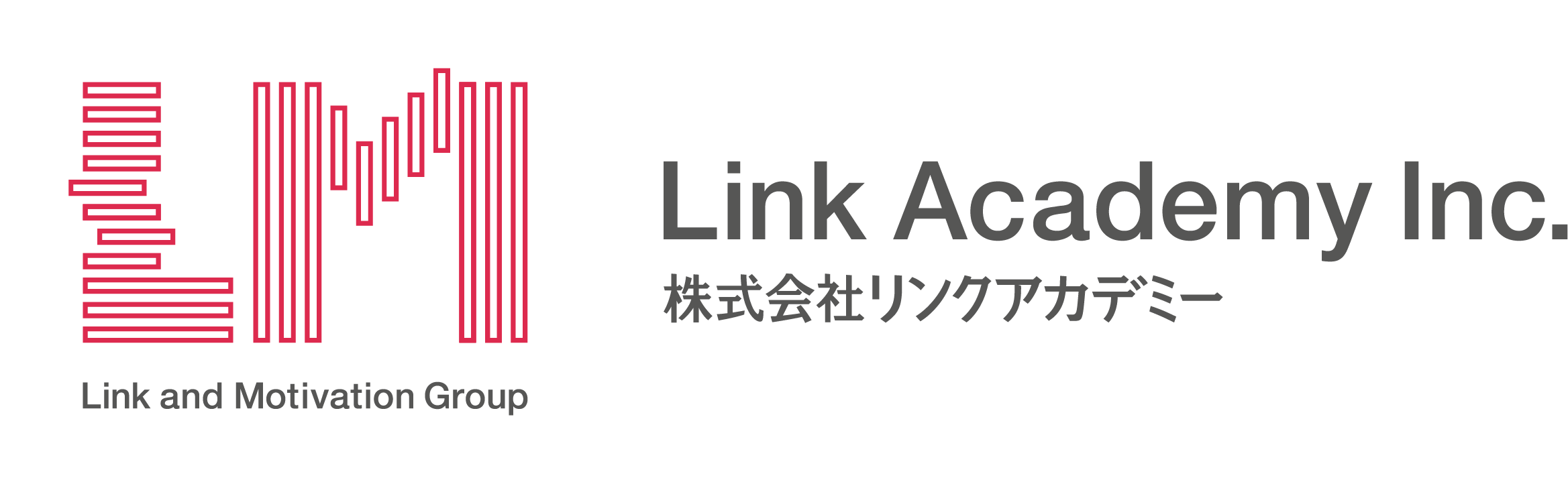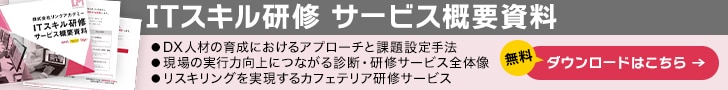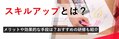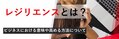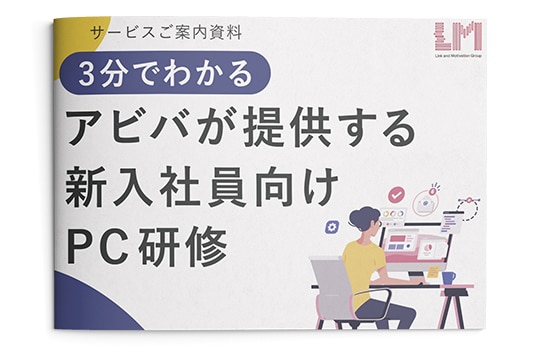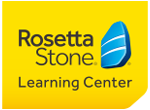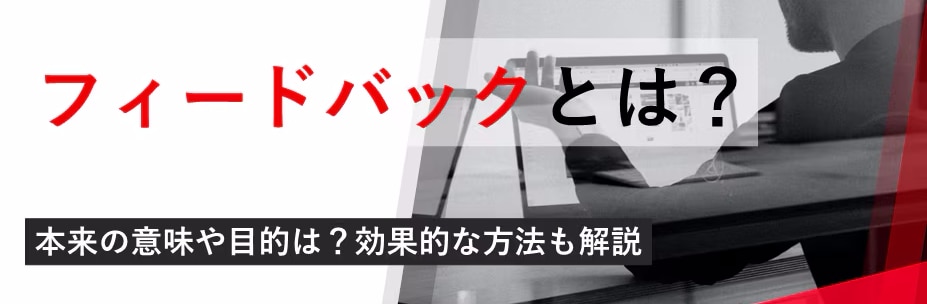
フィードバックとは?本来の意味や目的は?効果的な方法も解説
目次[非表示]
- 1.フィードバックとはどういう意味?
- 2.フィードバックの重要性
- 3.フィードバックにおける方向性は2つ
- 3.1.ポジティブフィードバック
- 3.2.ネガティブフィードバック
- 4.フィードバックの目的と効果
- 4.1.目標に対する軌道修正を行う
- 4.2.従業員のモチベーションを高める
- 4.3.スキルアップを促す
- 4.4.上司や会社に対する信頼を高める
- 5.フィードバックと似ている用語との違い
- 6.フィードバックの構成要素
- 7.【例文付き】フィードバックに使われる具体的な手法
- 8.フィードバックを効果的に行うためのポイント
- 8.1.目的や目標に繋がっていることをフィードバックする
- 8.2.具体的なことを伝える
- 8.3.人に対してではなく行動や事実に対して行う
- 8.4.タイムリーにフィードバックをする
- 8.5.明確な数値目標を設定する
- 9.フィードバックの効果を高めるためのスキル
- 10.社員教育ならリンクアカデミーがおすすめ
- 11.記事まとめ
- 12.フィードバックに関するよくある質問
仕事をしている中で、日常的に「フィードバックをする」機会は多いのではないでしょうか。フィードバックは人材育成や人事評価などの効果を高めるために採用されている方法ですが、フィードバックにはいくつか種類があり、その使い方にもポイントがあります。本記事では、フィードバックの種類や基本的な意味、メリットとその使い方のポイントなどをご紹介します。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
フィードバックとはどういう意味?
フィードバックとは、相手の行動に対して評価や改善点などを伝え、さらなる改善を促すことです。企業においては業務の振り返りや1on1面談、評価面談などでフィードバックを行う場合が多く、フィードバックを通して客観的に行動を振り返り、軌道修正を促すことができます。
元々フィードバックとは、「食べ物を与える」という意味の「feed」と「返す」「戻す」という意味の「back」から成り立っている言葉であり、制御工学やIT、教育学といった幅広い分野で用いられてきました。
ビジネスシーンにおけるフィードバックの意味
ビジネスにおいては、フィードバックは上司から部下へのアドバイスとしてイメージされることが多いでしょう。ビジネスシーンでフィードバックが行われる場面としては、下記のようなものが挙げられます。
■部下がミスをした場合
ミスに伴い、どのような出来事が起こっていたのかを確認した上で、原因の特定と次回以降再発しないためにはどのようなことが必要であるのかを本人と確認・相談しながらフィードバックを行います。
■業務でトラブルが起こった場合
トラブルが起こった原因を特定して、環境的な要因と人為的な要因などに整理をします。その上で、関係者に対して経緯や対策などのフィードバックを行います。
■従業員が成果を出した場合
ミスやトラブルといったネガティブな出来事に対してだけではなく、成果を出す、成功するといったポジティブな場面でもフィードバックを行い、その頑張りを賞賛します。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
フィードバックの重要性
人材育成におけるフィードバックの重要性
人材育成の方法としてフィードバックを活用することで、従業員が抱えている問題や直面している壁を把握して対応策を提示することができます。フィードバックがない状態では、従業員は自身の知識や主観の中でしか考えたり行動したりすることができないため、成長スピードが鈍化してしまう可能性があります。フィードバックを通して、客観的な意見やアドバイスを得られると従業員は自身の行動を見直して軌道修正がしやすくなるでしょう。
※更新日:2022/12/01
人事評価におけるフィードバックの重要性
人事評価においても、フィードバックを活用することは重要です。人事評価のために業務の状況や上司からの評価を収集した後に、従業員本人に評価の結果や理由を伝えない場合がしばしば見受けられます。評価に対するフィードバックが受けられない場合には、従業員は自身の評価に対する納得感が得にくくなるため、会社に対する信頼感が薄れてしまう可能性があります。
しっかりと人事評価のプロセスの中にフィードバック面談を設けることで、会社として求めることと従業員の認識を揃えることが大切です。
※更新日:2022/11/14
フィードバックにおける方向性は2つ
フィードバックの方向性として、大きく「ポジティブフィードバック」と「ネガティブフィードバック」の2種類が挙げられます。フィードバックをする状況に応じて使い分けることで、伝えるフィードバックの効果を高めることができるため、内容を把握しておきましょう。
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、結果や過程の中で相手の「良い点」や「ポジティブな面」に対してフィードバックを行うことを指します。肯定的な言葉を使ってポジティブフィードバックを行うことで、従業員は承認欲求が満たされて自信がつきやすくなります。ポジティブフィードバックの例としては、「今回のプロジェクトの中でこの点はすごく良かった」「あなたのこういう強みが活きていて素晴らしい」といった伝え方が挙げられます。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックは、結果や過程の中で「改善した方が良い点」や「ネガティブな面」に対してフィードバックを行うことを指します。ポジティブフィードバックと比べて従業員に対して否定的な言葉を用いることになりますが、適切に上司から見た改善点を伝えることで、客観的に自身の行動を見つめ直すきっかけになります。
ネガティブフィードバックは、伝えられる従業員によっては傷つく言葉だと感じることがあるため、伝え方には注意が必要です。伝え方として、まずポジティブフィードバックを行った上で「今後の成長のために伝えると・・・」「あなたのなりたい姿に対するアドバイスとして・・・」といった言葉を最初に伝えるやり方が効果的です。
フィードバックの目的と効果
目標に対する軌道修正を行う
フィードバックの大きな目的として、目標に対して適切に現状を把握して必要に応じて軌道修正を行うことが挙げられます。フィードバックによるアドバイスや助言から、目標に向けて上手くいかない原因やそれに対する解決策を検討することができます。特に管理職は部下に対して適切なフィードバックを行うことで、チーム全体が向かう方向性を調整する必要があります。適切なフィードバックを行うためにも、普段からのモニタリングやメンバーとの視界共有が重要になります。
従業員のモチベーションを高める
フィードバックには、従業員のモチベーションを高める効果があります。基本的に人間は自分がやったことに対する反応やリアクションが無い場合には、本当にやった事が正しいのか不安に感じます。この不安が大きくなると、従業員は放置されていると感じてしまうため注意が必要です。上司や周囲がフィードバックを行うことで、従業員は自分のことを見てもらえていると感じてモチベーションが高まるでしょう。
スキルアップを促す
フィードバックを行うことで、スキルアップを促すことも期待できます。フィードバックでは、上司や先輩は自身の経験やスキルに基づいてアドバイスや助言を行うことになります。そのため、部下が気づいていなかった観点や考え方を提供することで、視点が広がり自身の持っているスキルを伸ばすきっかけにすることができます。
※更新日:2022/12/01
上司や会社に対する信頼を高める
フィードバックを定期的に行うことで、従業員間のコミュニケーションの機会を増やすことができます。特に、フィードバックを通して従業員の悩みを解決したり、方針のすり合わせを行ったりすると、会社や上司への理解が深まります。理解が深まると、「会社の方針はこういう背景があったのか」「こういう理由で自分にアドバイスをくれるのか」といった感情が大きくなり、会社や上司に対する信頼感を高めることに繋がります。
フィードバックと似ている用語との違い
フィードバックと似ている用語として、フィードフォワード、レビュー、チェックバックがあります。ここでは、それぞれの意味やフィードバックとの違いについて簡単にご紹介します。
フィードバックとフィードフォワードの違いとは
フィードバックと似た言葉として、「フィードフォワード」があります。フォワードは、「前方」や「将来」といった意味を持つ「forward」から来ており、フィードフォワードは目標に対してできることや起こりうることについて話し合うことを指します。フィードバックが過去の出来事に対して原因の特定や改善策の提示を行うものであるのに対して、フィードフォワードは未来の出来事に対して先んじた助言や解決策の提示を行うものであるという点で違いがあります。
フィードバックとレビューの違いとは
評価や業務の振り返りの際には、「レビュー」という言葉もよく耳にします。レビューは「評論」「批評」といった意味を持つ「review」から来ており、ビジネスシーンでは「顧客からの感想」「業務に対する客観的な評価」といった意味で使われています。フィードバックがアドバイスや助言の意味合いが強いのに対して、レビューは純粋な感想や評価を提供する意味合いが強いといった点で違いがあります。
フィードバックとチェックバックの違いとは
フィードバックと似ている言葉として、「チェックバック」も挙げられます。チェックバックとは、英語では「check back」と書き、「振り返ってチェックをする」「遡って確認する」といった意味を持ちます。フィードバックと意味が似ていますが、チェックバックは主に映像関連の業界で用いられている言葉であり、映像作品の修正指示に伴って使用される言葉です。
フィードバックの構成要素
フィードバックは主に、「フィードアップ」「フィードバック」「フィードフォワード」の3つの要素で構成されています。それぞれの内容を把握しておくことで、フィードバックの効果を高めることができます。ここでは、それぞれについてその意味や内容を簡単にご紹介します。
フィードアップ:目的・目標の設定
フィードバックを構成する要素として、「フィードアップ」というものがあります。フィードアップとは、フィードバックの目的や目標を設定することを指します。目的や目標がないままにフィードバックを行うと、内容に一貫性や納得感が欠けてしまう可能性があります。
人材育成や組織の活性など、フィードバックの目的や目標を明確にすることでフィードバックの効果を高めることができます。また、既に目標がある場合にも、都度それを説明することが大切です。
フィードバック:経過の振り返り
フィードバックの効果を高めるためには、経過の振り返りを行うことが大切です。経過の振り返りとは、設定している目的や目標に対して、現在どのような状態であるのか、どのような行動を行ってきたのかといったことを振り返ることを指します。
経過の振り返りを行うことで、全体の中で今どこに位置しているのかを把握することができます。現在地の適切な把握を行うことができると、その後の活動の軌道修正などをより詳細に検討することができるようになるでしょう。
フィードフォワード:未来に向けた行動の検討
効果的フィードバックの構成要素として、未来に向けた行動の検討があります。これは、振り返りや評価などを行った後に、具体的にどのような行動をするのかを決めることを指します。未来に向けて、今のまま続けること、やめること、新しくやることを明確にすることで、フィードバックによる行動変化を生み出しやすくなります。
具体的なアクションを検討・実施することは大切ですが、多すぎると着手しづらくなるため、優先順位をつけることを意識しましょう。
【例文付き】フィードバックに使われる具体的な手法
SBI型
「SBI型」のフィードバックとは、「相手が置かれていた状況(Situation)」→「相手が行ったこと(Behavior)」→「結果として生じたことや影響(Impact)」の順番でフィードバックを行うことを指します。具体的に原因と結果を整理しながら伝えることができるため、フィードバックを伝えられる側としても納得感が高まりやすくなります。
■SBI型フィードバックの例
・Situation
「今回のお客様とのミーティングの時だけど」
・Behavior
「あなたが冒頭に今回の議題を伝えた上で、先方に何か気になっていることや悩んでいることを聞いてくれたね」
・Impact
「そのお陰で先方も気になっていることを解消できて、今日の本題にも集中して取り組んでもらえたよ。今後も色々なお客様に対して今日のような関わりをしてくれると助かるな」
KPT型
KPT型のフィードバックは、振り返りの手法としてもよく用いられているものです。KPTとは「Keep(継続して行うこと)」「Problem(上手くいかなかったことや今後はやめること)」「Try(今後新しくやること)」の頭文字を取ったものです。KPT型のフィードバックを用いることで、コミュニケーションの中で今後の行動を整理して明確にすることができるでしょう。
■KPT型フィードバックの例
上司:「今回のミーティングは自分で工夫をしていて良かったね。自分でも手応えがあったところはどこかある?」
部下:「それぞれの資料で伝えたいことを明確にしておけた点は良かったと思います」
上司:「シンプルで分かりやすくて良かったよ。全体の結論を導いてくれる資料だったから、次回からも メッセージを明確にすることを意識してくれると助かるな(Keep)。逆に自分で改善した方が良い点はあるかな?」
部下:「議論に時間をかけ過ぎて、終了時刻を過ぎてしまったことですね・・・」
上司:「結果として良い議論になったけど、それは改善点だね。議論を促すことは大切だけど、時間を把握して適宜進行をすることも大切だね。 あまり議論を委ね過ぎないようにしよう(Problem)。他に何か工夫できることはあるかな?」
部下:「 ある程度事前に考えて欲しいことを伝えておいて、その場で考え始めることを少なくしようと思います(Try)」
FEED型
FEED型のフィードバックは、「起こったことや相手の行動(Fact)」→「指摘をする理由(Example)」→「起こったことや行動による影響(Effect)」→「Different(今後の改善策や変えること)」の順番でフィードバックを行う方法です。FEED型のフィードバックを活用することで、出来事から次回への改善策まで一連の流れを理解しやすくなるでしょう。
■FEED型フィードバックの例
・Fact
「今度の 研修までの準備を進めてくれているよね」
・Example
「研修の準備の段取りについて、もっとスムーズに出来ると思うよ」
・Effect
「研修は講師や会場の手配のように、関係者との調整が必要だから、先に資料を作ることを優先していると、当日までに適切な手配ができなくなるかもしれないよ」
・Different
「これからは、まずは他のスケジュール調整が必要なことから優先して進めようか」
サンドイッチ型
サンドイッチ型のフィードバックとは、ネガティブな内容をポジティブな内容で挟んでフィードバックを行う方法です。ノースカロライナ大学のバーバラ・フレドリクソンの研究によると、「ポジティブ感情とネガティブ感情が3:1以上の割合であると、自己成長につながり幸福感が高まりやすい」といったことが分かっています。
最初に相手にとってポジティブな内容を伝えた上で、改善点や修正点を指摘し、最後に改めてポジティブな内容を伝えることで、自己成長につながりやすいポジティブとネガティブの比率を実現しやすくなります。
■サンドイッチ型フィードバックの例
・ポジティブ
「さっきのミーティングのために作ってくれた資料だけど、よくまとめられていて内容が分かりやすかったよ」
・ネガティブ
「ただ、プレゼン中の声のトーンが低く、話すスピードも速かったから少し内容が伝わりにくいかもしれないね」
・ポジティブ
「資料としてまとめられるスキルはあるから、それを伝えられるようなトレーニングをしよう」
ペンドルトンルール
ペンドルトンルールとは、心理学者であるペンドルトンが提唱したフォードバックの方法です。ペンドルトンルールのフィードバックでは、フィードバックを受ける従業員が自分で改善点を考えられるように促します。
ペンドルトンルールのフィードバックではコミュニケーションを密に取ることになるという特徴があります。上司が部下に対して一方的に改善点などを伝えるのではなく、部下が自分で振り返りや改善点の検討などを行うことで、主体的に行動を変えやすくなります。
■ペンドルトンルールのフィードバックの例
・シチュエーション
部下がミーティング資料の作成に時間がかかっており、期日に間に合わない状況が続いている
・フィードバック内容
「資料を期日内に作ることが難しいようだね。何か資料作成の際に活用できるフォーマットなどがあれば生産性が向上すると思うんだけど、自分ではどのようなものを作ればいいと思う?」
フィードバックを効果的に行うためのポイント
目的や目標に繋がっていることをフィードバックする
フィードバックは客観的な意見やアドバイスを行うことができ、本人の行動を変えるきっかけになりますが、無闇にフィードバックを行うと逆効果になることがあります。気になったこと全てを伝えてしまうと、「フィードバック過多」になりせっかくの助言も頭に入ってこなくなります
「目標から見て必要なフィードバックは何か」「どのように目標に対する軌道修正が行えるか」といったことを、フィードバックに対して考えるようにしましょう。
具体的なことを伝える
フィードバックによる軌道修正や行動改善を行うためには、具体的なことをフィードバックの中で伝えることが大切です。「資料が見づらかったから、次からは見やすくしておいて」や「売上の進捗が悪いから、なんとか頑張って」といった抽象的なフィードバックでは、フィードバックを受ける側はどのようにすれば良いのかわからない可能性があります。
「資料は1ページに1つのメッセージに絞って考えてみよう」、「売上を積み上げるために、まずは顧客を販売実績順にリストアップしてみよう」といった具体的な内容に言及しましょう。
人に対してではなく行動や事実に対して行う
フィードバックは人同士のコミュニケーションの中で行われるため、伝え方によっては「人格を否定された」「性格が悪いと言われている」といった様に、本人のパーソナリティへの否定として受け止められる可能性があります。人格や性格を否定されたと感じると、フィードバックに対して前向きに取り組むことはできず、会社や上司への信頼が薄れてしまうことになってしまいます。
フィードバックを伝える際には、人物そのものではなく、事実や行動に対して行うように意識しましょう。
タイムリーにフィードバックをする
行動をした後に時間が経つと、人はどんどんその内容を忘れていきます。また、時間が経った後に思い出したかのようにフィードバックされても、「今更言われても仕方がない」といった意識も芽生えやすくなり、フィードバックの効果が薄れてしまいます。そのため、フィードバックは、何か起こったタイミングでタイムリーに行うことが大切です。
明確な数値目標を設定する
評価者の主観や思い込みで判断するのではなく、アセスメントツール等を活用し明確な数値をもとにフィードバックを行うことで、偏った評価になることを防ぐ事が出来ます。
アセスメントツールは、従業員の能力や特性を数値をもとに客観的に測定し、評価することができるので、従業員の能力や特性、強みなどを可視化することができるので、アセスメントツールを用いたフィードバックは、従業員からの納得感も得られやすくなります。
リンクアカデミーでは、Excel Skill Surveyや、PowerPoint Skill Survey、 Degital Knowledge Surveyといった、個人のPCスキルや、ITナレッジを可視化する診断ツールを提供しています。
目的に合わせて、最適なアセスメントツールを活用することで、より効果的なフィードバックを行うことが出来るでしょう。
フィードバックの効果を高めるためのスキル
フィードバックを効果的に行う技術として、「ティーチング」と「コーチング」があります。教育や心理学の分野で有名な手法ですが、使い分けを行うことでフィードバックによる行動変化を促しやすくなるため、内容を確認しておきましょう。
ティーチングとは
ティーチングとは、直訳すると「教える」という意味になりますが、ビジネスシーンでは「業務に必要な手順や知識を教える」という意味として使われています。ティーチングは基本的に「正解を教える」というコミュニケーションになり、短期的な成果をあげたい場合に有効な手段です。
一方で、ティーチングだけに偏ってしまうと、「教えられるまではやらなくていい」といった指示待ちの状態になりやすくなるため、適切にコーチングと使い分けることが大切です。
コーチングとは
コーチングとは、直訳すると「指導する」という意味になりますが、ビジネスシーンでは「問題に対する解決策をコミュニケーションの中で考えてもらい、引き出す」という意味として使われています。ティーチングとは対照的に、「正解を教えずに、引き出す」というコミュニケーションになり、自主性や思考力を中長期的に育みたい場合に有効な手段です。
コーチングだけに偏ってしまうと、「分からないままで放置される」といった受け止め方になることがあるため、「まずは教えて、徐々に自分で考えてもらう」といった使い方をすると良いでしょう。
※更新日:2023/04/07
社員教育ならリンクアカデミーがおすすめ
ここまで、フィードバックについて触れてきました。フィードバックは、単なるアドバイスだけではなく、個人引いては組織全体の生産性を向上させる施策の1つです。
フィードバックの効果を最大化するためには、行う内容に加え、タイミングやフィードフォワードなどとの関連も重要になります。
しかし、大前提、フィードバックを行う人と受ける人が同じ視界を共有している必要があります。どんな目標に対して取り組んでいるのかなどが擦りあっていて初めて、適切なフィードバックを行うことができます。視界共有の方法は複数ありますが、可視化できるという点では表やスライドを用いることも効果的になります。
リンクアカデミーは「あなたのキャリアに、本気のパートナーを」をミッションに掲げ、「ティーチング」と「コーチング」のバランスをとることによって、個人が「学び」を通じ自らのキャリアを主体的に磨き上げられる場を目指しています。
多様化する個人のキャリアニーズに応えるべく、
・㈱アビバが提供してきたパソコンスキルの講座提供
・大栄教育システム㈱が提供してきた資格取得を支援する講座
・ディーンモルガン㈱が提供してきた「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」のマンツーマン英会話レッスン
といったキャリアアップに関するサービスをフルラインナップで展開してきました。
この実績と経験を活かして、
・内定者・新入社員の育成
・生産性向上
・営業力強化
・DX推進
といった幅広い課題に対して、お客様のご状況に合わせた最適なソリューションを提供しています。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
記事まとめ
フィードバックは行ったことや起こったことに対して、その評価や改善点などを伝えることを指します。フィードバックを行うことで、目標に対する軌道修正を促したり、従業員のモチベーションを向上したりすることができます。フィードバックを行う際には、目標との関連性をしっかりと確認し、人格否定にならないように気をつけることが必要であるため、ご紹介したフレームや例文を参考にして実践してみましょう。
フィードバックに関するよくある質問
Q1:フィードバックとは何?
A1: フィードバックとは、行ったことや結果に対してその評価や改善点などを口頭または文章などで伝えることを指します。企業においては業務の振り返りや1on1面談、評価面談などでフィードバックを行う場合が多く、フィードバックを通して客観的に行動を振り返り、軌道修正を促すことができます。
元々フィードバックとは、「食べ物を与える」という意味の「feed」と「返す」「戻す」という意味の「back」から成り立っている言葉であり、制御工学やIT、教育学といった幅広い分野で用いられてきました。
Q2:フィードバックにおける注意点は?
A2: フィードバックを行う際に注意するポイントは下記のものがあります。
■目的や目標に繋がっていることをフィードバックする
フィードバックは無闇にフィードバックを行うと逆効果になることがあります。「目標から見て必要なフィードバックは何か」「どのように目標に対する軌道修正が行えるか」といったことを、フィードバックに対して考えるようにしましょう。
■具体的なことを伝える
フィードバックによる軌道修正や行動改善を行うためには、具体的なことをフィードバックの中で伝えることが大切です。「資料は1ページに1つのメッセージに絞って考えてみよう」、「売上を積み上げるために、まずは顧客を販売実績順にリストアップしてみよう」といった具体的な内容に言及しましょう。
■人に対してではなく行動や事実に対して行う
フィードバックは本人のパーソナリティへの否定として受け止められる可能性があります。フィードバックを伝える際には、人物そのものではなく、事実や行動に対して行うように意識しましょう。
■タイムリーにフィードバックをする
行動をした後に時間が経つと、人はどんどんその内容を忘れていきます。フィードバックは、何か起こったタイミングでタイムリーに行うことが大切です。