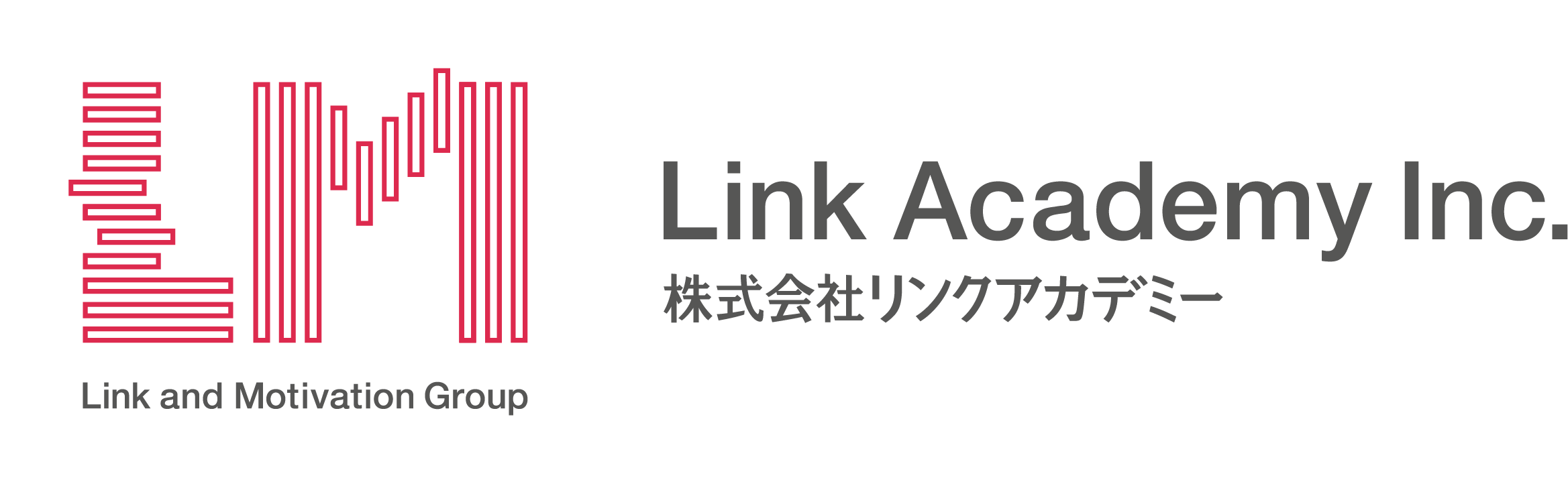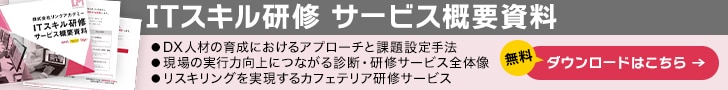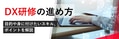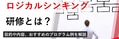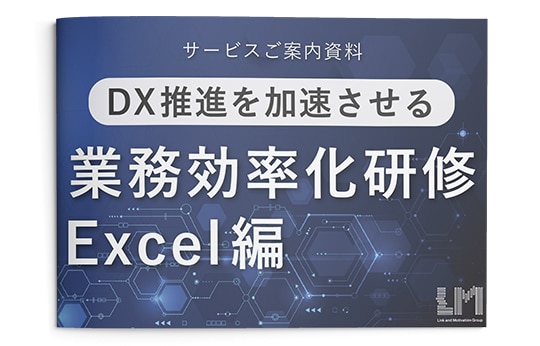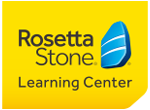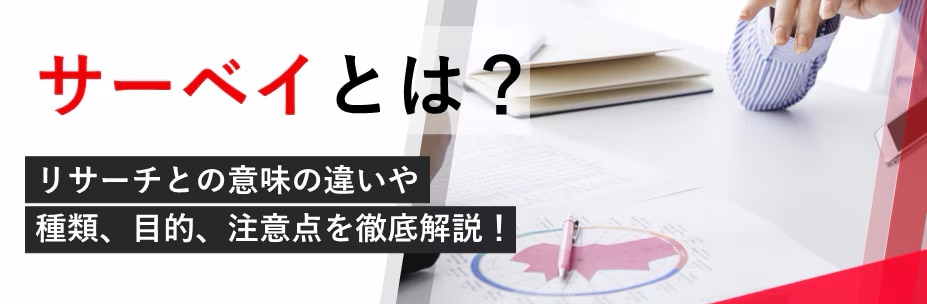
サーベイとは?リサーチとの意味の違いや種類、目的、注意点を徹底解説!
目次[非表示]
- 1.サーベイとは?
- 2.サーベイの種類
- 2.1.①従業員サーベイ
- 2.2.②パルスサーベイ
- 2.3.③エンゲージメントサーベイ
- 2.4.④モラールサーベイ
- 2.5.⑤コンプライアンス意識調査
- 2.6.⑥ストレスチェック
- 2.7.⑦スキルサーベイ
- 2.8.⑧組織サーベイ
- 2.9.⑨アセスメントサーベイ
- 3.実施頻度で分けられるサーベイの種類は?
- 4.サーベイの目的とは
- 5.サーベイが注目されている理由は?
- 6.サーベイのメリット・デメリット
- 6.1.サーベイのメリット
- 6.2.サーベイのデメリット
- 7.サーベイをうまく進めるためのポイント
- 7.1.サーベイの目的を明確にする
- 7.2.回答者の属性を決定する
- 7.3.調査の頻度を決定する
- 7.4.いくつかの回答方法を準備しておく
- 7.5.目的に合った設問を用意する
- 8.サーベイを実施する際の注意点
- 8.1.適切な設問内容にする
- 8.2.サーベイの事前説明を行う
- 8.3.匿名で回答できるようにする
- 8.4.フィードバックを必ず行う
- 8.5.回答までの期間をある程度確保する
- 8.6.経営サイドとのコミュニケーションをとる
- 9.法人研修のことならリンクアカデミーへ
- 10.リンクアカデミーの研修導入事例
- 11.まとめ
- 12.サーベイに関するよくある質問
近年は人的資本経営や、非財務資源の開示など人的資源を重要視した経営が注目されています。その中で、従業員や組織の状態を把握するために、サーベイが広く活用されるようになってきました。サーベイにはその目的によって種類があり、実施する際にはいくつか注意するべき点があります。本記事では、サーベイに関する基本的な知識やその実施のポイントなどをご紹介します。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
⇒ITスキル研修資料をダウンロードする
サーベイとは?
サーベイとは、「見渡す」「調査する」といった意味の英語である「survey」から来ている言葉であり、物事の全体像を把握するための調査のことを指します。ビジネスシーンでは、従業員の会社に対する意識や感じていることなどを把握するための調査という意味で使われています。
また、社内の調査だけではなく、社外の顧客やユーザーからの評価を調べるマーケティング活動においても、サーベイは用いられています。
リサーチとの違い
リサーチとは、サーベイと同様に「調査」という意味で使われていますが、ビジネスにおいては主にマーケティングの分野で用いられている言葉です。消費者・ユーザーに対する理解を深めるために、情報収集や研究を行います。
リサーチは、ある程度の条件や属性を持っている人を対象にして行われるケースが多く見受けられます。広い範囲の調査をサーベイで行い、課題やニーズを詳細に特定するためにリサーチが実施されます。
アンケートとの違い
アンケートも、サーベイと似ている言葉として挙げられます。アンケートは、顧客のリピート率や 研修の満足度などを調査するための方法を指します。アンケートは紙媒体のものやWeb形式のものなど、その実施方法には様々なものがあります。
アンケートは同様の質問を多くの人に行い、回答を集めることが一般的ですが、場合によっては5人〜10人程度の対象者を集めて座談会形式で実施することがあります。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
⇒ITスキル研修資料をダウンロードする
サーベイの種類
サーベイにはその実施目的や内容によって、いくつかの種類があります。代表的なものを確認しておきましょう。
①従業員サーベイ
従業員サーベイは、主に従業員の会社に対する満足度を把握するために行われる調査です。職場での人間関係や、待遇に関する満足度などが質問されることが多く、結果を基にして組織改善が行われます。
従業員サーベイを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 従業員が感じている問題や会社の課題を把握できる
- サーベイの結果に応じた対策で、生産性や従業員満足度を向上できる
従業員サーベイを行うことで、従業員が会社に対して満足・不満に思っていることを把握することができます。どのような部分に満足しており、どこに問題があるのかが明らかになることで、その対策を行うことができます。また、対策を行なって問題を解決することで、生産性を向上したり従業員満足度を向上したりすることができます。
②パルスサーベイ
パルスサーベイとは、高頻度で実施されるサーベイのことを指します。こちらも従業員満足度やエンゲージメントを調査する際に用いられており、一般的には毎週〜毎月の頻度で実施されます。パルスサーベイに対して、「センサス」という半年〜1年の頻度で実施されるサーベイもあり、これらはよく組み合わせて使われています。
パルスサーベイを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 組織改善の進捗状況を把握することができる
- 従業員満足度やエンゲージメントを高めることができる
パルスサーベイは高頻度でサーベイを実施するため、現在起きている問題や課題をすぐに把握することができます。従業員の満足・不満についても、リアルタイムで確認することができるため、自社の現状をすぐに知ることができることが強みです。
③エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、会社に対する深い関わり度合いや組織の方針への共感度合いであるエンゲージメントを調査するサーベイです。エンゲージメントは企業の生産性や離職率とも相関があるため、エンゲージメントサーベイを行うことで、業績の向上や人材定着に繋がります。
エンゲージメントサーベイを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 自社のエンゲージメントの状態を知ることができる
- エンゲージメントを向上することができる
エンゲージメントサーベイでは、理念やビジョン、仕事内容、上司、職場の環境など多面的な調査を行うことで、網羅的に組織状態を把握することができます。課題を特定して適切な施策を講じることで、エンゲージメントの向上を実現することができます。
▼エンゲージメントサーベイについて詳しい解説はこちら:「 エンゲージメントサーベイとは?従業員満足度調査との違い・効果・質問項目を紹介」
④モラールサーベイ
モラールサーベイとは、従業員のモラールを調査するサーベイのことを指します。モラールとは、「士気」や「意欲」という意味を持つ言葉であり、ビジネスでは労働意欲や団結意思といった使われ方をしています。
モラールサーベイを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 従業員の仕事に対する意識を把握できる
- 仕事に前向きに取り組むことができるようになる
モラールサーベイで従業員の士気や意欲を調査することで、目標に対しての意識や仕事への姿勢を把握することができます。従業員のモラールの状態に応じて対応することで、より仕事に対して前向きな意識をつくることができます。モラールはモチベーションやエンゲージメントとも関係するものであるため、組織づくりに大切な要素です。
⑤コンプライアンス意識調査
コンプライアンス意識調査では、コンプライアンスに対する従業員の意識・認識、感じている課題などを調査します。近年はインターネットの普及やSNSの発達などにより、一層従業員1人1人のコンプライアンス意識が大切になっています。
コンプライアンスに対する意識が低いと、場合によっては企業全体のブランドイメージの低下や売上の減少にも繋がるため、コンプライアンス意識調査を導入する企業が増えています。
コンプライアンス意識調査を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- コンプライアンスに関する知識や意識を高められる
- 会社のブランドやイメージを向上できる
調査を行うと、コンプライアンスに対してどのような意識があるかに加えて、そもそも気をつけるべきポイントについて学ぶことができます。従業員がコンプライアンスに対する知識を身に付けることで、企業のブランドイメージの向上に繋がります。
⑥ストレスチェック
ストレスチェックとは、従業員の精神衛生状態やストレス状態について把握する調査です。ストレスチェックは、50人以上の労働者がいる事業所については労働安全衛生法によりその実施が義務付けられています。
ストレスチェックを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 個人、職場の状態を把握できる
- ストレスによる不調を防止できる
ストレスチェックは従業員のメンタル的な状態について質問をするため、個人はもちろん職場全体がどのような精神状態であるのかを把握することができます。ストレスによる精神的・身体的な不調はその回復までに長い期間を要することが多いため、ストレスチェックにより未然に不調の原因を取り除くことが大切です。
⑦スキルサーベイ
ITの発達や人々の意識の変化に応じて、企業や個人に求められる知識やスキルも大きく変化してきています。新しい知識やスキルが必要になった時に、採用で人材を確保する事でカバーすることも可能ですが、金銭的なコストはもちろん、IT関連人材の中途市場の相場が高止まりしており、中途採用してもカルチャーフィットするのに時間がかかるという課題が発生しているのも現状です。
企業が主導となり、このような非連続的な変化に対応する自律的な人材の育成支援をしていく必要性が高まっている中で、今後必要とされるスキルに対し、組織または個人の現状のスキル可視化するためのツールとして、スキルサーベイが活用されています。
スキルサーベイを行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- 経営戦略に合わせて、従業員が必要とされるスキルを定量的に測定することで、現状課題を明確化することが出来る。
- スキルサーベイの結果をもとに、効果的に人材を育成できる。
- 従業員に健全な危機感を醸成できる。
人材育成においては、現在の業績や経営状況に加えて、事業や会社の方向性をもとに、「誰に」「何を」「どのような」スキルを獲得させるのかをデザインすることが重要です。
スキルサーベイを活用することで、戦略的な人材育成計画を立てられるだけでなく、より効果的に個人の習熟度に合わせた学習機会を効果的に提供することができます。
⑧組織サーベイ
組織サーベイとは、企業や所属する組織について問われるアンケート調査のことです。この調査を通じて、組織の現状や問題点を把握し、改善策を検討することができます。
組織サーベイを実施することで、以下のような効果が得られます。
組織の問題点を把握することができる
従業員からのアンケート結果を分析することで、組織の問題点を把握することができます。改善策の検討ができる
問題点が把握できたら、モチベーション向上やコミュニケーション改善などの具体的な改善策を検討することができます。従業員の意見を反映させることができる
組織サーベイを実施することで、従業員の意見を集めることができます。その結果、従業員が抱える問題や要望を把握し、それに応えることで、従業員の満足度向上につながります。
⑨アセスメントサーベイ
アセスメントサーベイとは、企業や組織内に所属する従業員の状態について問われるアンケート調査のことです。この調査を通じて、従業員の職務満足度やストレス、負荷度などの情報を把握し、改善策を検討することができます。
アセスメントサーベイを実施することで、以下のような効果が得られます。
職務満足度やストレスの把握ができる
従業員の状態を正確に把握することで、問題点を明らかにし、改善につながります。改善策の検討ができる
問題点が把握できたら、ワークライフバランスの改善や、ストレスの原因を取り除く施策を実施することで、従業員の生産性向上につながります。組織の成長につながる
アセスメントサーベイで得られた情報をもとに、組織全体の成長につながる施策を実施することで、従業員のモチベーションや生産性の向上につながります。
実施頻度で分けられるサーベイの種類は?
センサスサーベイ
センサスサーベイは、年に1回程度の頻度で、全ての従業員に対して行われるサーベイです。センサスサーベイのメリットは、全ての従業員の声を反映できることです。また、センサスサーベイの結果は、時間の経過によって変化することが少ないため、長期的な改善策の検討に活用することができます。
パルスサーベイ
パルスサーベイは、定期的に実施するサーベイで、短期的な改善策を検討するために行われます。パルスサーベイは、センサスサーベイに比べて時間とコストがかからないため、継続的な改善に向けた取り組みに適しています。また、従業員の声を定期的に聞くことで、問題が発生した場合に早期に対応することができます。
サーベイの目的とは
サーベイは様々な目的で利用されています。一般的には、従業員のエンゲージメントやストレス、コンプライアンスといった、組織の状態を把握するために行われています。サーベイを取ることはあくまで手段であり、その調査の後の組織変革を実現することがサーベイの目的です。
例えば、エンゲージメントサーベイを実施する際には、従業員エンゲージメントを高めて生産性を向上したり、離職率を適切な割合にしたりすることが目的となります。
サーベイが注目されている理由は?
近年、市場の環境は急速に変化しており、企業は常に変化に対応する必要があります。商品市場の短サイクル化・ソフト化や、労働市場の複雑化・多様化といった大きな変化が起きています。そんな中、企業には人のもつ力を組織の資源として最大限に引き出し、企業の成長につなげるといった「人的資本経営」の考えが必須となってきています。サーベイは、企業に属する従業員の状態を可視化するための手段として、今注目が上がっています。
また、環境が急速に変化する状況下で、従業員の意識の変化も起こっています。例えば、ワークライフバランスや福利厚生の充実、フレックスタイム制度の導入などが求められています。企業は、従業員のニーズに応えることで、優秀な人材を確保し、定着率の向上につなげることができます。企業はサーベイを通じて、従業員の働き方について真剣に考え、柔軟な働き方を促進することで、従業員のモチベーション向上や生産性向上に繋げることができます。
サーベイのメリット・デメリット
サーベイを実施することで、メリット・デメリットがあります。ここでは、代表的なものをご紹介します。
サーベイのメリット
サーベイのメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
■組織状態を可視化することができる
組織の状態が良いのか、悪いのかについて主観的な判断だけに偏ると、適切な組織運営ができない場合があります。サーベイを実施することで、網羅的に組織の状態を定量化・可視化することができるため、気づかなかった問題や課題を確認することができます。
■課題の優先順位を検討できる
従業員の人数や使える時間、お金と行った経営資源は有限です。資源を投下すべき対象の優先順位を誤ると、結果として利益の喪失や組織の疲弊を招きます。サーベイを行って実感していることと比較することで、取り組むべき課題に優先順位をつけやすくなります。
サーベイのデメリット
サーベイのデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
■従業員の負担になることがある
サーベイの種類、または実施方法にもよりますが、サーベイを準備・回答・回収することで、従業員の負担が増えることがあります。特に、設問数が多いサーベイの場合は繁忙期などと重なると回答に対するハードルが高くなるでしょう。
効率の能率を考慮したうえで、サーベイを実施するタイミングや、外部サービスに依頼するなどの実施方法を工夫することが必要となります。
■従業員の不満に繋がることがある
サーベイを実施することで、逆に従業員の不満を生み出すことがあります。基本的には通常の業務時間内に実施するため、従業員は「なんでこんなことをやっているんだ」と心理的な障壁が発生することが予想され、まさに「笛吹けども踊らず」の状況に陥りがちです。
そうならないためにも、しっかりとした動機付けをしたうえで、社内イントラでのトップからの発信など、仕組みを整備することで実効性の高い研修設計をすることも効果的です。
サーベイをうまく進めるためのポイント
サーベイをうまく進めるためには、いくつかのポイントがあります。しっかりとポイントを押さえて、効果的なサーベイ運用を目指しましょう。
サーベイの目的を明確にする
サーベイを実施するにあたって、その目的を明確にすることが大切です。目的が明確になっていないと、ただサーベイを実施するだけになってしまいます。企業の経営戦略と照らし合わせ、どのような組織状態になりたいのかを明確にしたうえで、適切なサーベイを実施することで、経営・現場共に組織変革にコミットすることができるでしょう。
回答者の属性を決定する
サーベイを実施する場合には、役職や年次といった回答者の属性を決めておくことをおすすめします。属性の種類を複数用意しておくことで、サーベイ結果の分析を様々な切り口から行うことができます。
部署や役職といった基本的な属性に加えて、入社年度や雇用形態といった属性を設定できるようにしておくと、組織改善を検討する際に考えやすくなるでしょう。
調査の頻度を決定する
サーベイを実施する際には、調査をする頻度を決定しておきましょう。調査の基本として、「調査する頻度は一定にする」ことが挙げられます。調査する頻度がまちまちである場合、それまでの結果と比較ができなくなってしまいます。突発的な要因がない限りは、できるだけサーベイの実施頻度は固定しておくことをおすすめします。
いくつかの回答方法を準備しておく
複数の回答方法を用意することで、回答者のニーズに合わせた方法を提供し、回答率を向上させることができます。また、異なる環境で回答する場合に生じる精度の差や、回答者が感じていることと回答項目とのずれを緩和し、回答データの精度を向上することもできます。企業が組織サーベイを進める上で、複数の回答方法を用意することは必須のポイントと言えます。
目的に合った設問を用意する
サーベイをうまく進めるためには、回答者が目的に合わせた回答をしやすいように、設問を用意することが重要です。例えば、従業員のモチベーション向上を目的とした場合には、モチベーションを向上させるための具体的な施策についての設問を用意することで、回答者が具体的なアイデアを出しやすくなります。
サーベイを実施する際の注意点
サーベイを実施する際には、気を付けておくべき注意点もあります。サーベイによる効果を保つために、代表的なものを押さえておきましょう。
適切な設問内容にする
サーベイを導入・実施する際には、設問内容が適切なものであるのかを確認しましょう。サーベイの設問が適切なものになっていない場合は、調査の網羅性や妥当性が失われてしまうことがあります。また、得たい回答を意識しすぎると、意図的に回答を誘導する質問になってしまうことがあるため、注意が必要です。
網羅的な設問内容になっているのかと、自社の実施目的に沿っているのかといったもののバランスを意識して、サーベイの設問内容を確認しましょう。
サーベイの事前説明を行う
サーベイをいきなり実施してしまうと、従業員にとっては「突然のお触れ書き」のようなものになってしまいます。サーベイの目的や内容、自分達への影響などが理解・共感できていない場合には、サーベイ自体に対する反発が生まれてしまい、望ましい効果が得られません。
サーベイを実施する前に、サーベイを実施する目的や内容、スケジュールなどを従業員に対して説明する機会を設けましょう。方法としては、共有会の実施やメールでの案内などが挙げられます。
匿名で回答できるようにする
サーベイを行う時には、目的に合わせ、匿名で回答できるようにするといった工夫も必要になる場合があります。記名式のサーベイの場合には、回答者が評価などに影響するのではないかと心配し、会社に感じている課題や問題点を指摘しづらくなります。回答に対する抵抗が生まれてしまうと、サーベイによる適切な現状把握ができなくなってしまうため、サーベイの効果が高まりません。
実施するサーベイの種類や目的に応じて、回答者の心理的障害をなるべく排除出来るような工夫をする事をお勧めします。
フィードバックを必ず行う
サーベイの効果を高められない理由として、「サーベイを取りっぱなしにしている」ことが挙げられます。サーベイは、基本的に個人にフィードバックをする機会を設けることや、人材育成計画に反映させることとセットです。サーベイを取ったとしても、その結果を受けて認識した課題やそれに対する対応策についてフィードバックを行わない場合には、従業員も不満を感じます。
サーベイを取った後には、時間が経ちすぎない内に従業員に対してのフィードバックを行い、サーベイの結果を企業の人材育成計画にも反映させましょう。
回答までの期間をある程度確保する
サーベイを実施する際には、回答までの期間をある程度確保することが重要です。回答者が十分な時間を持って回答することで、回答の質が向上し、回答率も向上するからです。また、回答期間を短く設定すると、回答者が回答するための負荷が大きくなり、回答を諦める場合もあります。
経営サイドとのコミュニケーションをとる
サーベイは取得して終わり、というわけではなく、その後の改善活動にしっかりと取り組むことが大切です。そのため、経営サイドとコミュニケーションを取り、組織改善に一体となって取り組むことができる環境を作ることが重要です。
法人研修のことならリンクアカデミーへ
国によるDX推進、そしてコロナ禍を背景に、企業はデジタル化を後回しにできなくなってきた中、リンクアカデミーでは、組織や個人のITスキルやナレッジを可視化するための、デジタルスキル・ナレッジサーベイを保有しています。
また、サーベイの結果をもとに、企業ごとに最適な研修プランのご提供まで、ワンストップでご支援させていただいております。
これまで
- ㈱アビバが提供してきたパソコンスキルの講座提供
- 大栄教育システム㈱が提供してきた資格取得を支援する講座
- ディーンモルガン㈱が提供してきた「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」のマンツーマン英会話レッスン
といったキャリアアップに関するサービスをフルラインナップで展開してきた実績と経験を活かして、
- 内定者・新入社員の育成
- 生産性向上
- 営業力強化
- DX推進
といった幅広い課題に対してソリューションを提供しています。
独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案
定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー
⇒ITスキル研修資料をダウンロードする
リンクアカデミーの研修導入事例
・ネットワンシステムズ株式会社様
・東京建物株式会社様
・株式会社フロム・エージャパン様
・株式会社トーコン様
まとめ
サーベイによる調査を行うことで、従業員満足度やエンゲージメント、コンプライアンスに対する意識などを把握することができます。適切に組織の現状を把握することで、組織改善を効果的に行うことができます。サーベイの種類によって、把握できる内容も変わるため、自社の目的に合わせて設問内容や実施頻度などを検討しましょう。
また、サーベイが従業員の負担や不満の原因とならないように、事前の目的説明や実施後のフィードバックなどに注意することをおすすめします。
サーベイに関するよくある質問
Q1:サーベイとは?
A1:サーベイとは、「見渡す」「調査する」といった意味の英語である「survey」から来ている言葉であり、物事の全体像を把握するための調査のことを指します。ビジネスシーンでは、従業員の会社に対する意識や感じていることなどを把握するための調査という意味で使われています。
また、社内の調査だけではなく、社外の顧客やユーザーからの評価を調べるマーケティング活動においても、サーベイは用いられています。
Q2:サーベイ・アンケート・リサーチの違いは?
A2:アンケート、リサーチとの違いはそれぞれ以下のようになっています。
■アンケートとの違い
アンケートは、顧客のリピート率や研修の満足度などを調査するための方法を指します。アンケートは紙媒体のものやWeb形式のものなど、その実施方法には様々なものがあります。アンケートは同様の質問を多くの人に行い、回答を集めることが一般的ですが、場合によっては5人〜10人程度の対象者を集めて座談会形式で実施することがあります。
■リサーチとの違い
リサーチとは、主にマーケティングの分野で用いられている言葉です。消費者・ユーザーに対する理解を深めるために、情報収集や研究を行います。リサーチは、ある程度の条件や属性を持っている人を対象にして行われるケースが多く見受けられます。広い範囲の調査をサーベイで行い、課題やニーズを詳細に特定するためにリサーチが実施されます。
Q3:サーベイを進めるポイントとは?
A3:サーベイを進める際には、しっかり現状が把握できて分析がしやすいように工夫をすることがポイントです。そのため、実施の目的を明確にすると共に、回答者の属性を複数にして分析の切り口を様々な方向で行うことができるようにします。また、実施頻度についてもまばらに実施するのではなく、時期を固定して複数回で比較ができるようにしましょう。