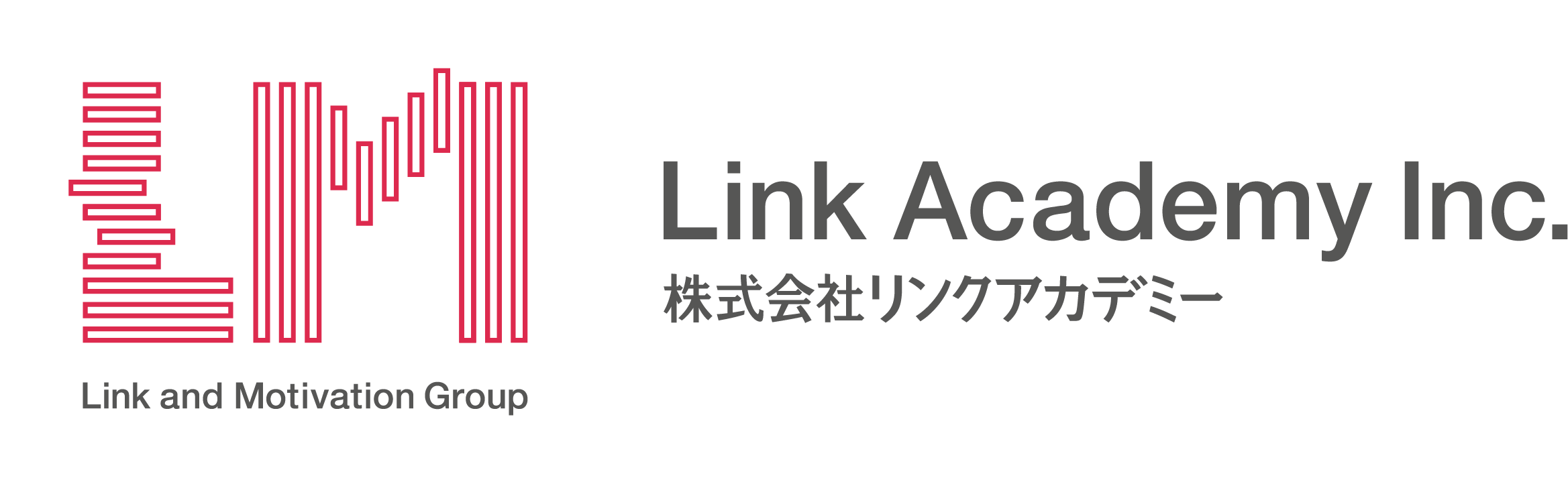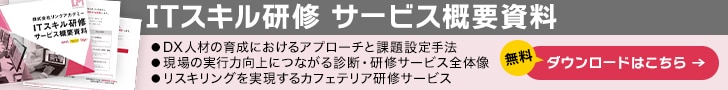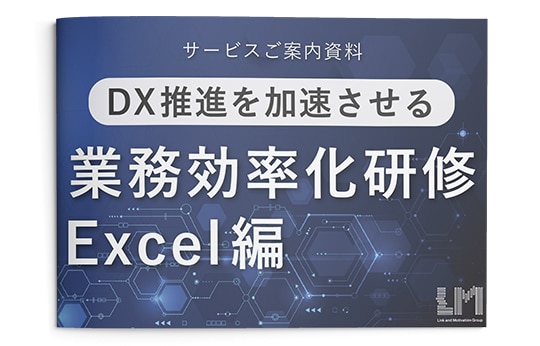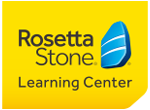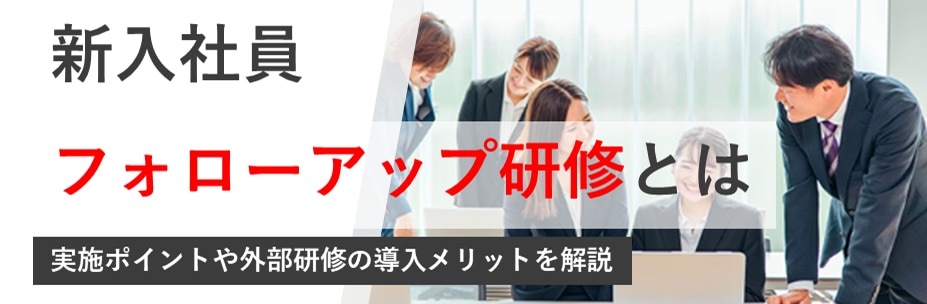
新入社員フォローアップ研修とは|実施ポイントや外部研 修の導入メリットを解説
目次[非表示]
- 1.新入社員フォローアップ研修とは
- 2.新入社員にフォローアップ研修を実施するメリット
- 3.新入社員フォローアップ研修を行う適切なタイミング
- 4.新入社員フォローアップ研修を成功させるポイント
- 5.新入社員フォローアップ研修のプログラム例
- 6.自社で新入社員フォローアップ研修を実施する際の課題
- 6.1.研修設計にノウハウが必要
- 6.2.社内講師のリソース不足
- 6.3.効果測定や改善が難しい
- 7.新入社員フォローアップ研修を外部に依頼するメリット
- 7.1.最新の教育ノウハウを活用できる
- 7.2.第三者視点のフィードバックが得られる
- 7.3.研修運営の負担を軽減できる
- 8.まとめ
- 9.
- 10.リンクアカデミーの研修導入事例
- 11.記事まとめ
新入社員研修を終えたあとも、業務や人間関係に戸惑いを感じる社員は少なくありません。研
修内容を現場で生かしきれず、成長の停滞や離職につながるケースも見られます。こうした課
題を防ぐために有効なのが、入社後の経験を整理し、今後の方向性を再確認できる「フォロー
アップ研修」です。
この記事では、実施の目的や効果を高めるための工夫、外部研修を導入する際のポイントを解
説していきます。
新入社員フォローアップ研修とは
新入社員フォローアップ研修とは、入社後しばらく現場を経験した社員を対象に、学びの定着
度や課題を整理し、さらなる成長へとつなげるための研修です。入社直後の研修で得た知識を
実務に照らし合わせ、理解を深める機会として位置づけられます。
また、社会人としての基礎から再確認しながら、今後の目標を明確にする場にもなります。研
修を通じて、個々の成長を促すだけでなく、組織として育成方針を見直す機会にもなり、人材
定着やパフォーマンス向上につながる重要な役割を担っています。
新入社員にフォローアップ研修を実施するメリット
フォローアップ研修を実施することで、日々の業務では得られない気づきや成長のきっかけを得られます。ここでは、新入社員の成長を支えるおもなメリットについて解説します。
入社後の経験を整理し課題を明確化できる
入社から一定期間が経過すると、実務を通じて得た知識や気づきが増える一方で、慣れによって自分のやり方が固定化し、課題が見えにくくなる傾向があります。フォローアップ研修では、自身の経験を振り返りながら、できている点と改善すべき点を整理します。
これにより、学びを定着させるとともに、次に伸ばすべきスキルや行動を具体的に考えるきっかけになります。
成長実感を得てモチベーションが持続する
日々の業務に慣れてくると、成長の実感を得にくくなる時期があります。フォローアップ研修では、入社時と現在を比較し、自分ができるようになったことを客観的に確認できます。努力の成果を実感することで自信が生まれ「次はこうなりたい」という意欲が高まり、前向きな姿勢を維持しやすくなるでしょう。
社会人としての意識や役割を再確認できる
業務を経験する中で目の前の仕事に追われ、社会人としての基本姿勢を忘れてしまうこともあります。フォローアップ研修では、組織の一員としての責任やチームへの貢献意識を再確認し、主体的な行動を促します。社会人としての自覚を高めることで、周囲との連携や信頼構築にもよい影響を与えます。
新入社員フォローアップ研修を行う適切なタイミング
フォローアップ研修の実施時期に明確な決まりはありません。しかし、社員の成長段階や課題が現れやすい時期を見極めて実施することで、より高い効果が得られます。ここでは、一般的に多い3つのタイミングについて解説します。
入社3か月後|業務に慣れ始めた時期に振り返る
入社から3か月ほど経つと、業務の流れや職場環境に慣れ始め、実務を通じた理解が進む時期です。この段階でのフォローアップ研修は、研修で学んだ内容の定着度を確認するよい機会となります。また、配属後に感じた戸惑いや不安を共有し、今後の成長課題を明確にする場としても有効です。
入社6か月後|成長の停滞期を打破する機会に
入社から半年が経過すると、初期の緊張感が薄れ、仕事に慣れた一方で成長の停滞を感じる社員も出てきます。フォローアップ研修を行うことで、自身の行動や成果を客観的に振り返り、次の目標を設定できます。中だるみを防ぎ、モチベーションを再び高める重要なタイミングといえます。
入社1年後|次年度へのステップアップを意識づける
1年が経過した新入社員は、一定の成果を出し始め、次の役割を意識する時期に入ります。この時期のフォローアップ研修では、1年間の経験を整理し、得た知識やスキルをどのように次年度へ生かすかを考えます。キャリア意識を高められれば、主体的に成長を続ける姿勢を育むことができるでしょう。
※更新日:2022/08/20
※更新日:2022/08/20
新入社員フォローアップ研修を成功させるポイント
フォローアップ研修を形だけで終わらせないためには、事前準備と運営の工夫が欠かせません。ここでは、効果を高めるための具体的なポイントを解説します。
事前にアンケートや面談で現状を把握する
フォローアップ研修の精度を高めるには、参加者の現状を正確に把握することが欠かせません。アンケートや面談で、業務中の課題や成長の実感、上司との関係性などを確認しておきましょう。事前準備が十分であれば、個々の課題に合わせた内容設計が可能になります。
課題や成果をチームで共有し成長を見える化する
フォローアップ研修では、個人の振り返りに加えて、チーム全体で成果や課題を共有することが効果的です。成功体験や悩みをオープンに話し合うことで、他者の視点から気づきを得られます。成果や行動目標を共有シートにまとめるなど、見える化の仕組みを導入します。
上司や先輩から建設的なフィードバックを受ける
上司や先輩のフィードバックは、受講者が次の成長へ進む大きなきっかけになります。努力を認められることで自信が生まれ、課題をより明確に捉えられるでしょう。重要なのは評価ではなく支援の姿勢です。成果だけでなく取り組みの過程にも目を向けることで、継続的な成長を促す文化が根づきます。
新入社員フォローアップ研修のプログラム例
フォローアップ研修では、入社後の経験を整理し、次のステップにつなげるための実践的なプログラムを組むことが重要です。ここでは、代表的な内容として取り入れられる3つのプログラム例について解説します。
入社後の経験を振り返るワーク
受講者それぞれが業務での成功事例や失敗体験を具体的に書き出し、発表・共有するワークです。グループ内でお互いの体験を比較しながら、どのような考え方や行動が成果を生んだのかを分析します。その後、改善点をまとめ、翌日から実践できるアクションプランを設定します。
単なる反省ではなく、自分の成長過程を客観的に捉えるトレーニングとして機能します。
課題解決をテーマにしたグループディスカッション
実際の職場で起こり得る課題(報連相の不足・顧客対応・時間管理など)をテーマに、チームごとに意見を出し合い、
原因分析と改善策を検討します。各グループが発表し合うことで、多様な視点からのアプローチを学べます。
議論の過程では、主体的な発言や傾聴力、論理的な整理力を磨くことができ、協働的な問題解決スキルの育成に役立つでしょう。
今後のキャリアプランを描くワークショップ
自分のキャリアを短期・中期・長期の3段階に分けて整理し、将来像を明確化するワークショップです。強みや価値観を棚卸しながら、今後1年間で達成したい目標を設定し、実現に向けた行動ステップを具体化します。
講師や上司によるアドバイスを受けつつ、キャリアへの意識を深める内容です。モチベーション維持と主体的な成長促進の両面で効果が期待できます。
自社で新入社員フォローアップ研修を実施する際の課題
フォローアップ研修を自社で完結させようとすると、設計・運営・評価の全てを社内で担う必要があり、さまざまな課題が発生するリスクがあります。ここでは、企業担当者が直面しやすい課題について解説します。
研修設計にノウハウが必要
研修を効果的に行うには、目的設定から内容設計、評価指標の策定まで、専門的なノウハウが欠かせません。担当者が多業務と兼任している場合、体系的なカリキュラム設計が難しくなりがちです。その結果、受講者の理解度やレベル差を踏まえた構成にならず、成果が曖昧になるケースもあります。
教育設計の知見を持つ人材の確保が課題といえるでしょう。
社内講師のリソース不足
社内で講師を確保しようとしても、教えるスキルを持つ社員が限られている場合が多く、担当者の負担が集中しやすくなります。指導経験が浅ければ内容が属人的になり、研修品質にばらつきが生じる恐れもあります。
また、通常業務と並行して準備・実施を行うことで時間的余裕がなくなり、継続開催が難しくなることも企業側の大きな悩みです。
効果測定や改善が難しい
社内で研修を実施しても「どの程度効果が出たのか」を定量的に把握できないと悩む企業は少なくありません。満足度のアンケートだけでは、行動変容や業績への影響を測れないためです。事前・事後評価の仕組みを設けなければ、改善の方向性も見えづらくなります。
成果を数値化するための評価設計や分析スキルが、今後の育成施策のカギになるでしょう。
新入社員フォローアップ研修を外部に依頼するメリット
自社での運営に限界を感じる場合、外部への依頼は有効な選択肢です。専門機関のノウハウや客観的な視点を取り入れることで、研修の質を高められます。ここでは、外部研修を導入するおもなメリットについて解説します。
最新の教育ノウハウを活用できる
外部研修を活用すれば、教育専門機関が持つ最新の教育メソッドを導入できます。社内では得にくいトレンドや他社事例、AI・DXなどの新テーマにも対応でき、時代に沿った内容で社員を育成できる点が大きな強みです。
講師は研修経験が豊富な専門家のため、理論と実践を結びつけた効果的な学びを受けられます。
第三者視点のフィードバックが得られる
外部講師が介在することで、社内では見落としがちな課題や改善点を客観的に指摘してもらえます。上司や同僚からの評価とは異なり、第三者の視点で得られるフィードバックは受講者の納得感を高めます。中立的な立場だからこそ、現場の課題にも踏み込んだ建設的な助言を得ることも可能です。
研修運営の負担を軽減できる
企画・日程調整・教材作成といった運営業務を外部機関に委託することで、担当者の作業負担を大きく減らせます。少人数の人事部門でも安定して研修を実施でき、他の業務に集中しやすくなるでしょう。準備から効果測定までを一括でサポートしてもらえるため、品質と効率を両立した運営が実現します。
まとめ
フォローアップ研修は、入社後の経験を整理し、社員が主体的に成長していくための重要なステップです。研修を継続的に運用することで、早期離職の防止や組織全体の生産性向上にもつながります。ただし、社内だけで効果的に設計・実施するのは容易ではありません。
外部の専門機関を活用することで、最新の教育手法を取り入れながら、限られたリソースでも高品質な研修を実現できます。社員育成を中長期的な視点で捉えるなら、フォローアップ研修に加えて、ITリテラシーやDX対応力を高める教育も欠かせません。
リンクアカデミーの「ITスキル研修 サービス概要資料」では、DX人材育成に向けた課題設定の考え方や、実行力を高める研修プログラムの全体像を紹介しています。組織全体のスキル底上げを検討する際には、ぜひご覧ください。
※更新日:2022/11/14
リンクアカデミーの研修導入事例
・ネットワンシステムズ株式会社様
・東京建物株式会社様
・株式会社フロム・エージャパン様
・株式会社トーコン様
記事まとめ
インターネットやデバイスの普及により、従来の学習方法からeラーニングによる学習が発展してきました。eラーニングによって、これまでの学習方法とは異なり「いつでも・どこでも」学習ができるのに加えて、管理者側もその進捗状況や学習教材の管理がしやすくなりました。ただ、eラーニングを導入する際にも注意点があること、他の学習方法と組み合わせることで更に学習効果を高めることができるということも認識しておく必要があります。