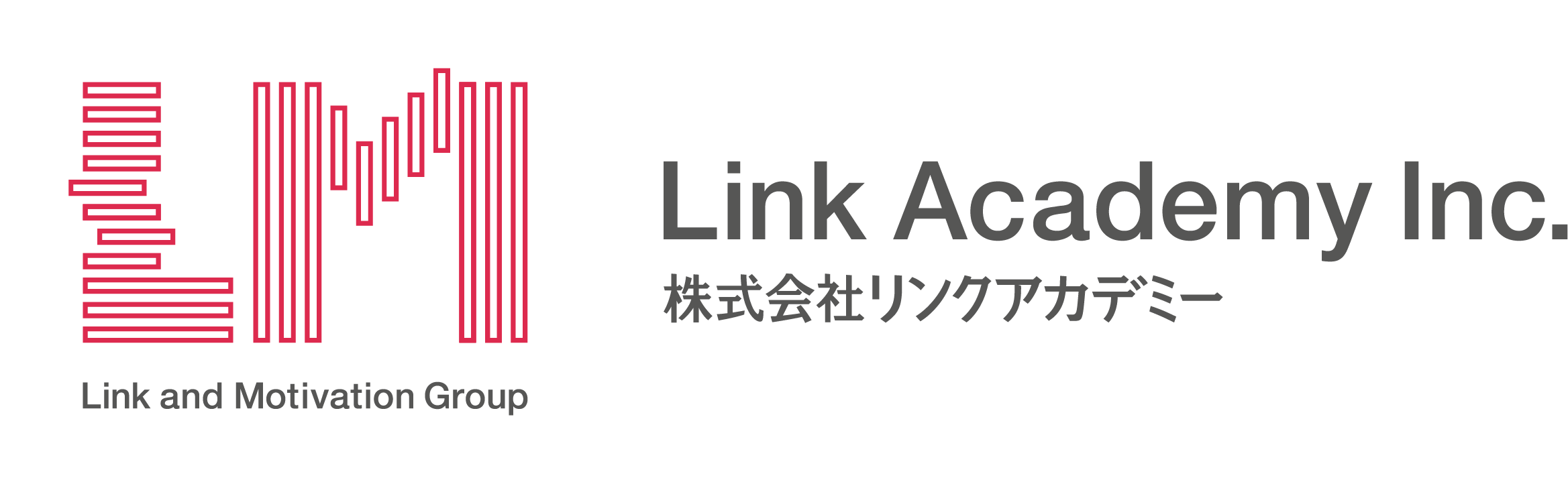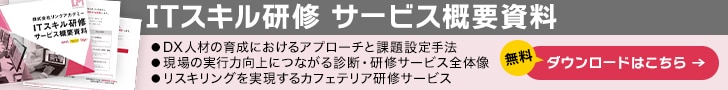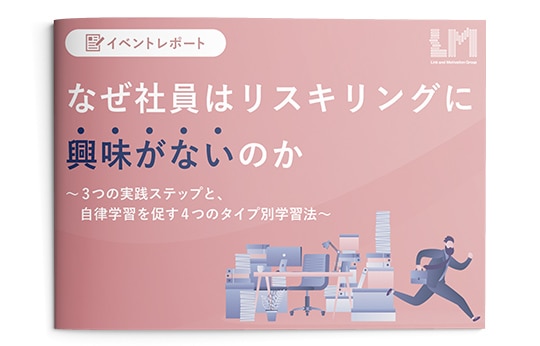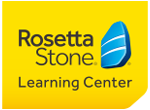ロジカルシンキングとは?メリット・考え方・実践方法を紹介
目次[非表示]
- 1.ロジカルシンキングとは
- 1.1.そもそもロジカルとは
- 2.ロジカルシンキングとクリティカルシンキングとの違い
- 3.ロジカルシンキングとラテラルシンキングとの違い
- 4.ロジカルシンキングが重要視されるようになった背景
- 5.ロジカルシンキングのメリット
- 5.1.分析力が向上する
- 5.2.課題解決力が向上する
- 5.3.提案力が向上する
- 5.4.コミュニケーション力が向上する
- 5.5.生産性が向上する
- 6.ロジカルシンキングの基本の考え方
- 6.1.MECE
- 6.2.So What?/Why so?
- 7.ロジカルシンキングのフレームワーク
- 8.ロジカルシンキングにおける論理展開
- 9.ロジカルシンキングの効果的なトレーニング方法
- 9.1.フェルミ推定問題でトレーニング
- 9.2.書籍を活用してトレーニング
- 9.3.Excelを活用してトレーニング
- 10.ロジカルシンキングを身に付けるためのトレーニングのコツ
- 10.1.日常的に取り入れる
- 10.2.ゼロベース思考を習慣化させる
- 10.3.結論から話すことを意識する
- 10.4.仮説を立てて考える
- 10.5.セルフディベートを行う
- 11.ロジカルシンキングを実践する際の注意点
- 11.1.結論に至るまでのプロセスを明確にする
- 11.2.自分自身の思考に疑問を持つ
- 11.3.情報を正確に把握する
- 12.ロジカルシンキングを応用した手法
- 12.1.①ロジカル・コミュニケーション
- 12.2.②ロジカル・プレゼンテーション
- 13.ロジカルシンキング強化研修ならリンクアカデミー
- 14.リンクアカデミーの研修導入事例
- 15.記事まとめ
- 16.ロジカルシンキングに関するよくある質問
ロジカルシンキングとは、物事を矛盾がないように体系的に整理し、結論を出す思考方法のことです。ロジカルシンキングは業務を遂行する中で生じる課題の解決や、事業における問題の解決策の検討などに役立つ思考法であるため、多くの企業で研修や講座によるトレーニングを実施しています。一方で、ビジネスで役に立つ思考法は様々な種類があるため、違いが分からなくなることもあるのではないでしょうか。本記事ではロジカルシンキングの基本的な考え方や、他の思考方法との違い、実践方法などをご紹介します。
ロジカルシンキングとは
そもそもロジカルとは
ロジカルとは、論理的、筋道立てて考えることを意味します。「ロジカルである」という状態は、論理的思考を用いて問題を解決していることを指します。ロジカルな考え方では、感情や主観的な意見に基づく判断ではなく、客観的な事実や論理的なプロセスに基づいた判断を行います。また、「ロジカル」という言葉は、ビジネスや科学、技術分野など、多くの分野で一般的な言葉として用いられています。
ロジカルシンキングとクリティカルシンキングとの違い
ロジカルシンキングと似ている言葉として、クリティカルシンキングが挙げられます。クリティカルシンキングは「批判的思考」とも訳されるため、一見「粗探し」や「間違い探し」といった意味に受け取られることがあります。しかし、クリティカルシンキングの目的は「本当に正しいことは何かを見極めること」です。これに対して、ロジカルシンキングは「論理的に筋道を立てて整理すること」が目的になっているため、批評的な姿勢はクリティカルシンキングよりも少ないでしょう。
▼クリティカルシンキングの詳しい解説はこちら
ロジカルシンキングとラテラルシンキングとの違い
「ラテラル」とは、「横方向」や「水平」を意味する「lateral」という英語から来ています。そのため、ラテラルシンキングとは「水平思考」とも呼ばれており、物事を多角的に考えることを意味しています。ラテラルシンキングは「新しい発想を生み出すこと」を目的としているため、様々な思考の材料を活用します。これに対してロジカルシンキングは「垂直思考」とも呼ばれており、「ある一定の枠組みの中で思考すること」になる点でラテラルシンキングとは異なります。
ロジカルシンキングが重要視されるようになった背景
現代社会において情報化が進む中で、多様な情報が簡単に手に入るようになりました。しかしその一方で、情報量が膨大になり、正確な情報の選択や判断が難しくなっています。このような状況下で、ロジカルシンキングの重要性がますます高まっています。
また、グローバル化が進む中で、異文化間のコミュニケーションや仕事においても、ロジカルシンキングは必要不可欠なスキルです。異なる文化や価値観を持つ人々とのコミュニケーションにおいては、感情的な思考や主観的な判断が誤解を生むことがあります。一方で、ロジカルシンキングに基づいた判断は、より正確かつ客観的で、相互理解につながることが期待できます。
ロジカルシンキングのメリット
分析力が向上する
ロジカルシンキングを身につけるメリットとして、分析力の向上が挙げられます。ビジネスで生じる問題は様々な要因が影響して引き起こされている場合が多いため、その構造を理解して原因を分析することが必要です。ロジカルシンキングの思考方法を活用することで、以下の様に分析をすることができるようになります。
■問題に関する情報を収集する
■事実を適切に把握する
■問題や考えられる原因の分類を行う
■問題と原因の因果関係を考える
課題解決力が向上する
ロジカルシンキングを身につけることで、分析力の向上と共に課題解決力も向上することができます。問題に対する原因を分析したとしても、それぞれの問題に対する解決策を考えて実行することができなくては次につながりません。そのため、ロジカルシンキングの思考方法を活用することで以下のように課題解決を実行することができます。
■生じた問題に対して、どのような原因がどの程度影響しているかを考える
■判断基準を設けて、取り組む課題の優先順位をつける
■課題解決のための方法を洗い出す
■方法を整理して取り組むべきことを決める
提案力が向上する
ロジカルシンキングは自身で物事を考えること以外にも、他者に対して提案する際にも役立ちます。自身の考えを提案する際には、相手にとって分かりやすい論理的な説明や筋道の立った話が重要です。ロジカルシンキングの思考方法を活用することで、以下のように提案力を向上できるでしょう。
■相手の感じている課題を把握する
■自身の考えや意見を筋道を立ててまとめる
■相手に論理的な説明をする
■疑問や懸念を整理して解決策を伝える
コミュニケーション力が向上する
提案活動だけではなく、ロジカルシンキングはコミュニケーション力の向上にも有効です。コミュニケーションは「受信」と「発信」で構成されており、自分の考えだけを伝えることはそれほどないでしょう。むしろ相手の意見を引き出し、お互いの考えを合わせて考えることでより良い結果に繋がることは少なくないでしょう。その際に、しっかりと意見の整理や分析ができないと考えをまとめることは難しくなってしまいます。ロジカルシンキングの思考方法を活用することで、目的に沿った提案活動を行うことができます。
▼コミュニケーションの詳しい解説はこちら
生産性が向上する
ロジカルシンキングを身に付けることで、問題の分析やその解決策の立案、解決に向けた協力を得るための提案や交渉などを効率的に行うことができます。業務の中で既存のやり方を踏襲することは必要ですが、環境の変化や顧客の要望などに合わせてやり方を変える必要がある場合があるでしょう。その際にはロジカルシンキングの思考方法によって、構造を適切に理解してより良い手段を考えることができるようになります。
※更新日:2022/11/14
ロジカルシンキングの基本の考え方
MECE
論理的な思考ができているかを判断する際に、「MECEになっているか」を確かめる機会があるのではないでしょうか。MECEとは、「Mutually(お互いに、相互に)」「Exclusive(被らず、重複せず)」「Collectively(まとまって、全体的に)」「Exhaustive(漏れなく)」の頭文字を略したものであり、「モレなく、ダブりなく」という意味で使われています。
例えば、「動物園にいる動物を分類する」というテーマでMECEの考え方を確認してみましょう。この際、「キリン」「ゾウ」などといった動物名で数え上げることもできますが、この方法ではモレが生じてしまう可能性があります。一方で、「哺乳類」「鳥類」といった生物学状の種類で分類をすることで、漏れやダブりを防ぎやすくなります。
MECEはこのように全体像を捉えて、要素を整理することができます。MECEを活用することで、問題や解決策などを網羅的に考えることができるでしょう。
So What?/Why so?
MECEと共にロジカルシンキングの基本的な考え方として、「So What?/Why so?」も挙げられます。「So What?」は「つまり何か?」、「Why so?」は「なぜそうなのか?」といった意味を持っています。これらは問題や解決策などを考える際に問いかける形で、So What?」は結論を、「Why so?」は原因を詳細に深掘りするために使われています。
例えば、「寝坊をしないためにはどうしたらいいのか」といったテーマで「So What?/Why so?」を考えてみましょう。
「寝坊をする」という事象に対して、「Why so?」を考えると、「寝る時間が遅い」「日中運動をしていない」といったように原因を考えることができます。更に「Why so?」を続けると、「夜中に動画を見過ぎて寝る時間が遅くなる」「日中外に出る機会が無い」といったように深掘りをすることができます。ここから、「寝る前に動画を見る時間を少なくする」「日中に外に出る」といった解決方針を立てることができます。
次に、「寝る前に動画を見る時間を少なくする」「日中に外に出る」に対して「So What?」を考えてみましょう。この場合は「つまり、どうしたら良いのか?」を考えると、「動画アプリの時間制限機能を活用する」「昼食など外に出る用事を作る」といったように深掘りをすることができるでしょう。
ロジカルシンキングのフレームワーク
ピラミッド構造
ピラミッド構造とは、結論をピラミッドの頂点としてその下にその根拠を階層状に並べて整理するフレームワークです。結論や仮説に対する根拠を考える際に、バラバラに考えているとモレやダブりが生じてMECEではなくなり、大切な論理を飛ばした思考になってしまう可能性があります。ピラミッド構造では、結論の下に根拠を分解して深掘りをする思考を繰り返すため、結論を根拠で支えることができるようになります。
ピラミッド構造を考える際には、結論から根拠を考えていく「トップダウンアプローチ」だけではなく、根拠から出発して結論へと積み上げていく「ボトムアップアプローチ」があります。トップダウンアプローチは、ある程度自身の中に「こうではないか?」といった仮説がある際にその妥当性を考える際に有効です。一方で、ボトムアップアプローチは問題が複数生じている時に、そこから導かれる結論や仮説を見つける際に有効です。
ロジックツリー
ロジックツリーとは、課題やテーマに対してそれに連なるツリー(枝)を考えて分解することで分析や課題解決を行う方法です。ロジック(論理)の繋がりを意識せずに考えると、結論や仮説が飛躍したものになってしまう可能性や、モレやダブりが生じてMECEではなくなってしまう可能性があります。ロジックツリーを考える際には、下記のポイントに注意することが必要です。
・ロジックツリーを構成するものの水準がバラバラにならない
ロジックツリーは階層ごとに水準が揃っている方が効果的です。「いちご」「スイカ」「メロン」のように食べ物の名前を並べている階層で「とちおとめ」のように商品名が入ると水準が揃っていないことになります。
・ロジックツリー全体の要素で逸脱したものが入らない
ロジックツリーは頂点に来るテーマや課題に沿ったもので構成する必要があります。「動物園にいる生き物」を分解している中で、「いちご」のように食べ物が入ると、テーマから逸脱した要素が入ったロジックツリーになってしまいます。
・要素を分解する際には切り口に固執しすぎない
ロジックツリーを考える際には切り口を設定する必要があります。しかし、上手く深掘りや分解ができない場合には、最初に設定した切り口に固執せずに様々な切り口を試してみることが必要です。
ロジックツリーには「要素分解」「原因究明」「イシューの抽出」を目的としたものがあるため、それぞれご紹介します。
要素分解
要素分解を行うロジックツリーは、「Whatツリー」とも呼ばれています。要素分解のロジックツリーは、「動物園にいる動物を分類する」や「自社の売上構成は何か」というように、テーマや課題を構成している要素を洗い出して整理する際に用いられています。
要素分解のロジックツリーを考えることで、複数の要素を比較して違いを見つけたり、要素自体を具体化することができます。
原因究明
原因究明を行うロジックツリーは、「Whyツリー」とも呼ばれています。原因究明を行うロジックツリーは、「寝坊をしてしまう」や「売り上げが低迷している」といったテーマや課題の原因を洗い出して整理する際に用いられています。
何か問題が生じた時に、すぐに思いつく原因があるとしてもそれが本当に原因になっているかは経験や勘に頼ってしまっている場合があります。原因究明のロジックツリーを考えることで、原因を網羅的に検討することができるでしょう。
イシューの抽出
イシューの抽出とは、取り組むべき課題や解決策を決めることを指しています。イシューの抽出を行うロジックツリーは「Howツリー」とも呼ばれており、「寝坊を防ぐ」「売上を増やす」といったテーマや課題の解決方法を洗い出して整理する際に用いられています。
ロジックツリーを活用せずに解決策を決めてしまうと、効果的では無い解決策に時間を使ってしまう可能性があります。ロジックツリーでしっかりとイシューを抽出して解決策を比較検討することで、優先順位を決めることができるでしょう。
ゼロベース思考
ゼロベース思考とは、何かを考える際に、過去の経験や前提条件にとらわれず、まっさらな状態から考えることを指します。
つまり、前提条件や既存の枠組みにとらわれず、物事を新たな視点から見つめることができるため、新しいアイデアや革新的な解決策を生み出すことができます。このような思考法は、ビジネスやイノベーションなどで活用されています。
ロジカルシンキングにおける論理展開
帰納法
帰納法とは、「複数の事実からその傾向や共通点を分析することで結論や一般論を導き出すこと」を指しています。例えば、「7月は売上が向上した」「7月から8月にかけて問い合わせが増えている」といった複数の事実がある場合は、「夏場には売上が上がりやすい」といった一般論を導き出すことができます。
帰納法を活用することで、より課題やテーマに対するアプローチを考えやすくなりますが、ここで「帰納法は現在確認している事実から共通点や傾向を導いた1つの仮説である」ということに注意が必要です。今回の例では2つの事実から「下半期は売上が良い」という一般論を導き出すことができるかもしれません。更に、他にも情報を収集して「10月にも売上のピークがある」といった事実が判明した場合には「3ヶ月ごとに売上が良くなる」といった一般論にすることができるでしょう。
帰納法は推測をして見通しを立てることに有効ですが、まずは情報をしっかりと集めて充分な数の事実から行うことが大切です。
演繹法
演繹法とは、帰納法とは逆に「一般的論やルールから結論を導き出すこと」を指しています。例えば、演繹法として下記のような例が有名です。
・人間には寿命がある
・ソクラテスは人間である
・ソクラテスはいつか死ぬ(結論)
このように、複数の一般論から結論を導くことができます。これに対して帰納法では下記のようになるでしょう。
・ソクラテスが死んだ
・ソクラテスは人間である
・人間には寿命がある(結論)
演繹法は帰納法とは異なる過程で思考をするため、それぞれを使い分けることで課題やテーマに対してより効果的なアプローチができるようになるでしょう。一方で、演繹法は「一般論が正しいという前提で成り立っている」ということに注意が必要です。一般論が間違っている場合には結論も妥当ではない可能性があるため、演繹法を活用する際にも「この一般論は主観ではないか」「正しい情報を扱っているか」といったことを確認することが大切です。
ロジカルシンキングの効果的なトレーニング方法
フェルミ推定問題でトレーニング
ロジカルシンキングをトレーニングする際に有名な方法の1つが「フェルミ推定」です。物理学者のエンリコ・フェルミがこのフェルミ推定の思考方法を得意としていたため、この名前が使われています。フェルミ推定は、「実際には分からないものに対して、分かっているものを手掛かりにして推論すること」を指しています。
例えば、フェルミ推定の有名な問題として、「アメリカのシカゴにはピアノ調律師は何人いるか」というものがあります。ピアノ調律師の登録制度が無い場合には、シカゴ中のピアノ調律師を数え上げることは現実的には難しいでしょう。その際には下記のような情報を基にしてフェルミ推定を行います。
■活用する情報やデータ
・シカゴには300万人が住んでいるとする
・1世帯あたりには平均で3人いるとする
・10世帯に1台の割合でピアノを保有しているとする
・ピアノの調律は1年に1回のペースで行うとする
・調律師は1日に3台のピアノを調律することができるとする
・調律師は年間で250日働くとする
■データからの推論
・「世帯数」=300万(人)/ 3(人)=100万(世帯)
・「ピアノの数」=100万(世帯)/ 10(世帯)=10万(台)
・「1年間で調律されるピアノの数」=250(日)× 3(台)=750(台)
・「ピアノ調律師の数」=10万(台)÷ 750(台)=約130(人)
書籍を活用してトレーニング
ロジカルシンキングのトレーニングをする方法として、書籍を活用することも有効です。ロジカルシンキングは「そもそもフレームを知らない」「フレームは知っているが、具体的に使ったことがない」といった場合には、上手く活用することができません。書籍を活用して繰り返し練習をすることで、日常生活やビジネスシーンでも自然と使うことができるようになるでしょう。
ロジカルシンキングを学ぶ書籍の選び方としては、下記のような基準を参考にすると良いでしょう。
・ロジカルシンキングの手法の全体像を学びたい→入門書で概要を知る
・ロジカルシンキングの実践練習をしたい→ドリル形式の演習本で反復練習を行う
・ビジネスで活用できるフレームを知りたい→ケースワークをベースにした専門書で練習する
Excelを活用してトレーニング
本記事のテーマである「ロジカルシンキング」の必要性を社会人になって、より強く感じる人は多いのではないでしょうか。自身の行動計画を立てる時、お客様へ商品サービスを紹介する時、上司への報告をする時など、幅広いシーンで役立つロジカルシンキングの力は社会人にとって必須のスキルです。
このスキルを身に着けるための方法として、日々の思考訓練はよく聞くところですが、日常的に使用するExcelの学習がロジカルシンキング習得・強化にも繋がることはご存じでしょうか?
Excelは日常業務でもよく使用するツールですが、関数や計算に偏って使用しているシーンが多くあります。しかし実は意外と知られていない目的から逆算する機能が備わっているのです。例えばExcel上の表やピボットテーブルなどのデータや関数を駆使することで、状況把握と問題分析ができるようになります。
そういった機能を駆使し、原因究明のために思考することによって、目的からの逆算思考が身につけられたり、ロジカルシンキング習得に向けての一歩に繋がります。
※更新日:2022/11/14
ロジカルシンキングを身に付けるためのトレーニングのコツ
ロジカルシンキングを身につけるためには、いくつかのトレーニング方法があります。日常的にトレーニングを取り入れることで、ビジネスシーンでもスムーズにロジカルシンキングを実行することができるようになります。ここでは、代表的なトレーニングについてご紹介します。
日常的に取り入れる
ロジカルシンキングを身につけるためには、日常的な練習が不可欠です。例えば、考えを整理するためにメモを取ったり、問題解決に向けて段階的に行動するように心がけたりすることが挙げられます。また、常に自分の意見を主張する前に、相手の意見に耳を傾けることも大切です。
さらに、論理的に考えるためには、自分の意見を正確に表現する能力を高める必要があります。そのためには、自分の考えを書き出したり、口頭で表現したりする練習を積むことが重要です。
また、ロジカルシンキングを身につけるためには、異なる問題やチャレンジに直面することも大切です。例えば、さまざまなトピックについて読んだり、新しい趣味を試したり、討論や議論に参加したりすることが挙げられます。
ゼロベース思考を習慣化させる
ゼロベース思考は、既存の枠組みに縛られることなく、全く新しいアイデアを見出すための思考法です。このアプローチを取り入れることで、過去の経験や前提条件にとらわれず、より創造的で独創的なアイデアを生み出すことができるようになります。
また、ゼロベース思考を習慣化させることで、常に新しい視点から物事を見つめることができるようになります。例えば、毎日少しの時間を割いて、自分の興味のあるテーマについて、ゼロベース思考を取り入れた考え方を模索することができます。
結論から話すことを意識する
ロジカルシンキングにおいては、結論から話すことが重要です。これは、自分が伝えたいことを明確にするためだけでなく、相手にもわかりやすく伝えるために必要なことです。
この際に、PREP法を活用することができます。PREP法とは、「P(Point):結論」「R(Reason):理由」「E(Example):具体例」「P(Point):結論の再確認」で構成されたプレゼンテーションのノウハウです。PREP法を使うことで、問題を明確にし、原因を特定し、それによって生じる影響を理解し、最終的に対策を考えることができます。
仮説を立てて考える
ロジカルシンキングにおいて、仮説を立てることが重要です。仮説を立てることで、自分自身が持つ前提条件やアイデアについて考え、新しい発見やアイデアを生み出すことができます。例えば、仮説を立てた後に、仮説に矛盾があるかどうか、また、仮説に基づいた実験や調査を行うことで、仮説を検証することができます。
このように、仮説を検証することで、より正確な判断ができるようになります。さらに、仮説を立てるというプロセスは、創造性を高めるためにも役立ちます。
セルフディベートを行う
セルフディベートとは、自分自身に対して反論や批判をすることを指します。これにより、自分自身が持つ前提条件やアイデアについて客観的に見ることができ、より正確な判断ができるようになります。また、自分自身に対して厳しい意見を持つことで、自分自身の成長にもつながります。
セルフディベートは、自己批判の方法としても知られています。自分自身に対して批判的になることで、自分自身の弱点や欠点を発見し、改善することができます。
ロジカルシンキングを実践する際の注意点
ロジカルシンキングはビジネスシーンにおいて大変役に立つ思考方法ですが、ロジカルシンキングを実践する際にはいくつか注意するべき点があります。ロジカルシンキングの注意点を把握しておき、実践する際に意識するようにしましょう。
結論に至るまでのプロセスを明確にする
ロジカルシンキングにおいては、自分自身や他者に自分の考え方を説明しやすくするために、結論に至るまでのプロセスを明確にすることが重要です。
プロセスを明確にすることで、自分自身が持つ前提条件や仮定を明確にし、より正確な判断ができるようになります。ロジカルシンキングを身につけることで、より正確な判断力を身につけ、ビジネスや学術分野など、様々な分野で活躍できるようになります。
自分自身の思考に疑問を持つ
ロジカルシンキングを実践する際に重要なのは、自分自身の思考に疑問を持つことです。自分自身の思考に疑問を持つことで、より客観的に自分自身の考え方を見つめることができます。これによって、より正確な判断ができるようになります。
自分自身が考えたことが全て正しいといった前提を捨てて、本当に妥当性があるかどうかを振り返る習慣をつけることが大切です。例えば、立てた仮説が正しいのかをデータをもとにして判断したり、他の人から意見をもらったりといったことが有効です。
情報を正確に把握する
ロジカルシンキングにおいては、情報を正確に把握することが重要です。情報を正確に把握することで、より正確な判断ができるようになります。また、情報を正確に把握することで、不必要な誤解や誤解釈を避けることができます。情報化が進む現代社会においては、ますます多様な情報が簡単に手に入るようになりました。
しかし、その一方で、情報量が膨大になり、正確な情報の選択や判断が難しくなっています。このような状況下で、ロジカルシンキングの重要性がますます高まっています。
ロジカルシンキングを応用した手法
ロジカルシンキングは、様々な手法に応用することができます。ロジカルシンキングを応用することで、コミュニケーションやプレゼンテーションなどを効果的に実施することができます。ここでは、ロジカルシンキングを応用した手法をご紹介します。
①ロジカル・コミュニケーション
ロジカル・コミュニケーションとは、相手に対して論理的かつ合理的なコミュニケーションを行うことを指します。ロジカル・コミュニケーションを行うことで、相手に対して自分の意見を正確かつ明確に伝えることができ、相手の理解を深めることができます。
②ロジカル・プレゼンテーション
ロジカル・プレゼンテーションとは、論理的かつ合理的なプレゼンテーションを行うことを指します。ロジカル・プレゼンテーションを行うことで、聴衆に対して自分の意見を正確かつ明確に伝えることができ、聴衆の理解を深めることができます。
ロジカルシンキング強化研修ならリンクアカデミー
関数や計算といったExcelの基本の使い方を習得することはもちろん、先述した目的から逆算する機能など、日常的に使用するツールであるExcelを機能ごとに使い分けられるようになることで「時間の短縮」だけでなく「原因究明に向けた論理的思考力を身に着ける」ことも可能になります。
本記事のテーマである「ロジカルシンキング」は短期間ではなかなか身に着けることが難しいのが事実です。物事を論理的に考えるためには、自身の思考スキルの向上だけではなく、日常的に使用するツールへの理解を深め、備わっている機能を使って逆算するという手段も持っておきましょう。
弊社リンクアカデミーでは、基本から応用までExcelの正しい使い方を体系的に習得できる「基本研修・応用研修」から、業務効率化を実現させるための「Excel活用研修」、データから正しく根拠を導くための「データ分析・原因究明研修」など、幅広いソリューションをご用意しています。
▼ロジカルシンキング研修の詳しい解説はこちら
※更新日:2022/11/14
リンクアカデミーの研修導入事例
・ネットワンシステムズ株式会社様
・東京建物株式会社様
・株式会社フロム・エージャパン様
・株式会社トーコン様
記事まとめ
社会人に必須のスキルである「ロジカルシンキング」は多くの人が身に着けたいと考えるスキルでしょう。しかし、短期間で身に着けることが難しいものであるため、日常的且つ長期的にトレーニングを行うことで徐々に能力の向上を測る必要があります。
一方、ロジカルシンキングの重要ポイントである「逆算」という観点でみると、Excelのような日常的に使用しているツールの中にも自動で逆算ができる知られていない便利なツールも存在するということをご紹介させていただきました。
Excelを使いこなし、作業時間の短縮及び思考の強化をしていきましょう。
ロジカルシンキングに関するよくある質問
Q1:ロジカルシンキングとは?
A1:ロジカルシンキングとは、論理的思考とも言われており、物事を筋道立てて考えたり、適切に分類や整理を行ったりする思考方法のことを指します。ビジネスにおいて問題発見や課題解決などに役立つロジカルシンキングですが、主に下記のような要素が含まれています。
■言葉や数字の定義を正しく行う
■物事の分類やラベリングを行う
■判断基準を明確にする
■物事の関係性を構造的に捉える
■決めつけではなく、情報から事実を正しく抽出する
Q2:ロジカルシンキングの手順は?
A2:ロジカルシンキングの基本的な思考の方法として、「帰納法」と「演繹法」があります。帰納法とは、「複数の事実からその傾向や共通点を分析することで結論や一般論を導き出すこと」を指しています。例えば、「7月は売上が向上した」「7月から8月にかけて問い合わせが増えている」といった複数の事実がある場合は、「夏場には売上が上がりやすい」といった一般論を導き出すことができます。
演繹法とは、帰納法とは逆に「一般的論やルールから結論を導き出すこと」を指しています。例えば、演繹法として下記のような例が有名です。
・人間には寿命がある
・ソクラテスは人間である
・ソクラテスはいつか死ぬ(結論)
また、これらの思考方法をベースとして、「ピラミッド構造」や「ロジックツリー」といったフレームワークを活用することでロジカルシンキングの手順を辿ることができるでしょう。